(はじめに)
この第5部では、「ヨーロッパアルプス」にある、具体的な山や山群の地質について、スイスなどのオンライン地質図を元に、解説します。
具体的には、ヨーロッパアルプスのうち、4000m以上の高峰群が多く、日本の登山者、観光客にもなじみが深い、「中部アルプス」の、「ベルナーオーバーラント山群」(the Berner Oberland massif)、「ヴァリス山群」(the Vallis massif)、「モンブラン山群」(the massif of Mont Blanc)について、やや詳しめに解説します(筆者自身も何回か訪れていて馴染みがあるという理由もあります)。
またそれら以外にも「ヨーロッパアルプス」には、登山、ハイキング、観光の対象として良く知られている山群があります(文献5)。
そのうち、スイス東部の「ベルニナ山群」(Bernina massif)、フレンチアルプス(「西部アルプス」)のうち、「グランパラディ―ソ山群」(Grand Paradiso massif)、「エクラン山群」(Ecrins massif)、及び「東部アルプス」の一部も、地質解説をする予定です。
なお、この第5部では、各山、山群の地質については、主にスイスのオンライン地質図(文献2A、2B)を参照しました。それ以外には、オーストリアのオンライン地質図、フランスのオンライン地質図も、ある程度参照しました。
(参考文献)の項に上げた各種文献も、記載の参考としています。
具体的には、ヨーロッパアルプスのうち、4000m以上の高峰群が多く、日本の登山者、観光客にもなじみが深い、「中部アルプス」の、「ベルナーオーバーラント山群」(the Berner Oberland massif)、「ヴァリス山群」(the Vallis massif)、「モンブラン山群」(the massif of Mont Blanc)について、やや詳しめに解説します(筆者自身も何回か訪れていて馴染みがあるという理由もあります)。
またそれら以外にも「ヨーロッパアルプス」には、登山、ハイキング、観光の対象として良く知られている山群があります(文献5)。
そのうち、スイス東部の「ベルニナ山群」(Bernina massif)、フレンチアルプス(「西部アルプス」)のうち、「グランパラディ―ソ山群」(Grand Paradiso massif)、「エクラン山群」(Ecrins massif)、及び「東部アルプス」の一部も、地質解説をする予定です。
なお、この第5部では、各山、山群の地質については、主にスイスのオンライン地質図(文献2A、2B)を参照しました。それ以外には、オーストリアのオンライン地質図、フランスのオンライン地質図も、ある程度参照しました。
(参考文献)の項に上げた各種文献も、記載の参考としています。
5−1章 「ベルナーオーバーラント山群」の地質
(はじめに)
「ベルナーオーバーラント山群」(the Berner Oberland massif)は、「ベルニーズアルプス」(Bernese Alps(英))や「ベルナーアルプス」(Berner Alpen(独))とも呼ばれますが(文献7)、スイス中部に位置し、多くの4000m峰を有する山群です。麓には有名なリゾート地「グリンデルワルド」(Grindelwald)があり、その周辺を含め、世界中の観光客、ハイカー、登山者に人気の山域です(文献4)、(文献5)。
「ベルナーオーバーラント」という地域名は、元々「ベルン州の奥の山岳地域」といった意味あいですが、そのうちの登山、観光の対象となっている山地名である「ベルナーオーバーラント山群」(ベルニーズアルプス)の範囲は、文献等によって違いがあります。南側の境界は東西に伸びる「ローヌ谷」(Rhone valley)で、北側の境界は、インターラーケン
(Interlaken)の町を通る東西のラインという点では一致していますが、東西の境界をどこに採るかは様々です。
例えば、現地の登山ガイドブックである(文献6)では、西端をマルティニ(Martiny)〜モントルー(Montreux)を通る谷(ローヌ川)とし、東端はグリムゼル峠(Grimsel pass)の更に東側の、3000m級の山々の一部まで含めています(東西幅 約180km)。
ウイキペディア英語版(文献7)では、西端はマルティニ〜モントルーを通る谷とし、東端は、マイリンゲン(Meiringen)の町〜グリムゼル峠を通る谷(アーレ川)としています(東西幅 約100km)。
日本の観光ガイドブックである(文献4)では、西端をカンデル谷(Kandeltal)〜ゲンミ峠(gemmi pass)のラインとし、東端をマイリンゲンの町〜グリムゼル峠のラインとしています(東西幅 約60km)。
この章では、(文献4)の範囲を(狭義の)「ベルナーオーバーラント山群」とし、その中の山々のうち、特に4000m級の山々と、グリンデルワルド周辺の高原地帯(アルプ)を中心に説明します。広義および狭義の「ベルナーオーバーラント山群」の範囲は、図1をご参照ください。また(狭義の)「ベルナーオーバーラント山群」主要部の地形図と主な山の位置は、図2をご参照ください。
この山域の主な山としては、いわゆる「ベルナーオーバーラント三山」と呼ばれている、「アイガー」(Eiger;3967m)、「メンヒ」(Monch;4110m)、「ユングフラウ」(Jungfrau;4158m)が有名です。また「グリンデルワルド」のすぐ北東側には、「ヴェッターホルン」(Wetterhorn; 3690m)がそびえています。添付の図2もご参照ください。
それら、いわば表舞台側にある山々の奥には、限られたクライマーしか訪れない4000m級の高峰群が多数あります。4000m以上の主な山を列挙すると、この山群最高峰の「フィンスターアールホルン」(Finsteraarhorn;4274m)の他、「フィッシャーホルン(Fisecherhorn;4049m)、「シュレックホルン」(Schreckhorn;4078m)、「アレッチホルン」(Aletschhorn;4194m)、「グリュンホルン」(Grunhorn;4043m)、「ラウターアールホルン」(Lauteraarhorn;4042m)などがあります。(注1)。それらの山の場所は、添付の図7をご参照ください。
なお、本格的な登攀ガイドブックである(文献6)には、3500〜4000m級の山々も含め、70以上の登攀対象の山々が記載されています。
またそれらの奥山群の間には、多くの氷河や氷食谷があります。その中でも「ヨーロッパアルプス」最長の長さを誇る「アレッチ氷河」(the Aletsch Gletscher)は有名です。「アレッチ氷河」とその周辺は、ユネスコの「世界遺産」にも登録されています(文献8)。
一方、グリンデルワルドの周辺は、ロープウエイなどで容易に上がれる、2000〜3000m前後の、アルプ(alp)とも呼ばれる高原地帯となっています。
例えば、「フィルスト」(First;約2200m)、「メンリッヘン」(Mannlichen;2342m)、「クライネシャイディック」(Kleine Scheidegg;約2100m)、「シルトホルン」(Schilthorn;2970m)、「ミューレン」(Murren;約1600m)などは、ロープウエイや登山電車で容易に上がれる展望台、ハイキングコースの起点として、良く知られています(文献4)、(文献5)。
この章では、スイスのオンライン地質図(文献2A、2B)を元に、上記の高峰群およびグリンデルワルド近郊のハイキングゾーンの地質について、説明します。
「ベルナーオーバーラント」という地域名は、元々「ベルン州の奥の山岳地域」といった意味あいですが、そのうちの登山、観光の対象となっている山地名である「ベルナーオーバーラント山群」(ベルニーズアルプス)の範囲は、文献等によって違いがあります。南側の境界は東西に伸びる「ローヌ谷」(Rhone valley)で、北側の境界は、インターラーケン
(Interlaken)の町を通る東西のラインという点では一致していますが、東西の境界をどこに採るかは様々です。
例えば、現地の登山ガイドブックである(文献6)では、西端をマルティニ(Martiny)〜モントルー(Montreux)を通る谷(ローヌ川)とし、東端はグリムゼル峠(Grimsel pass)の更に東側の、3000m級の山々の一部まで含めています(東西幅 約180km)。
ウイキペディア英語版(文献7)では、西端はマルティニ〜モントルーを通る谷とし、東端は、マイリンゲン(Meiringen)の町〜グリムゼル峠を通る谷(アーレ川)としています(東西幅 約100km)。
日本の観光ガイドブックである(文献4)では、西端をカンデル谷(Kandeltal)〜ゲンミ峠(gemmi pass)のラインとし、東端をマイリンゲンの町〜グリムゼル峠のラインとしています(東西幅 約60km)。
この章では、(文献4)の範囲を(狭義の)「ベルナーオーバーラント山群」とし、その中の山々のうち、特に4000m級の山々と、グリンデルワルド周辺の高原地帯(アルプ)を中心に説明します。広義および狭義の「ベルナーオーバーラント山群」の範囲は、図1をご参照ください。また(狭義の)「ベルナーオーバーラント山群」主要部の地形図と主な山の位置は、図2をご参照ください。
この山域の主な山としては、いわゆる「ベルナーオーバーラント三山」と呼ばれている、「アイガー」(Eiger;3967m)、「メンヒ」(Monch;4110m)、「ユングフラウ」(Jungfrau;4158m)が有名です。また「グリンデルワルド」のすぐ北東側には、「ヴェッターホルン」(Wetterhorn; 3690m)がそびえています。添付の図2もご参照ください。
それら、いわば表舞台側にある山々の奥には、限られたクライマーしか訪れない4000m級の高峰群が多数あります。4000m以上の主な山を列挙すると、この山群最高峰の「フィンスターアールホルン」(Finsteraarhorn;4274m)の他、「フィッシャーホルン(Fisecherhorn;4049m)、「シュレックホルン」(Schreckhorn;4078m)、「アレッチホルン」(Aletschhorn;4194m)、「グリュンホルン」(Grunhorn;4043m)、「ラウターアールホルン」(Lauteraarhorn;4042m)などがあります。(注1)。それらの山の場所は、添付の図7をご参照ください。
なお、本格的な登攀ガイドブックである(文献6)には、3500〜4000m級の山々も含め、70以上の登攀対象の山々が記載されています。
またそれらの奥山群の間には、多くの氷河や氷食谷があります。その中でも「ヨーロッパアルプス」最長の長さを誇る「アレッチ氷河」(the Aletsch Gletscher)は有名です。「アレッチ氷河」とその周辺は、ユネスコの「世界遺産」にも登録されています(文献8)。
一方、グリンデルワルドの周辺は、ロープウエイなどで容易に上がれる、2000〜3000m前後の、アルプ(alp)とも呼ばれる高原地帯となっています。
例えば、「フィルスト」(First;約2200m)、「メンリッヘン」(Mannlichen;2342m)、「クライネシャイディック」(Kleine Scheidegg;約2100m)、「シルトホルン」(Schilthorn;2970m)、「ミューレン」(Murren;約1600m)などは、ロープウエイや登山電車で容易に上がれる展望台、ハイキングコースの起点として、良く知られています(文献4)、(文献5)。
この章では、スイスのオンライン地質図(文献2A、2B)を元に、上記の高峰群およびグリンデルワルド近郊のハイキングゾーンの地質について、説明します。
5−1章―(1)節 「ベルナーオーバーラント山群」の地質、地形概要
「ベルナーオーバーラント山群」の地質構成は、上記の「ベルナーオーバーラント三山」付近を通る北東―南西走向の「地質境界線」を境として、大きく2グループに分けられます。添付の図3(ベルナーオーバーラント三山付近の地質図)もご参照ください。
上記の「地質境界線」(図3の赤い線)の北西側は、地質的には「ヘルベチカ系」地質グループ(the Helvetic nappe system)(文献1−3)の分布域で、中生代(主に「ジュラ紀」、一部は「白亜紀」)の堆積物層と、それが部分的に変成作用を受けた地質体からなります。
スイスのオンライン地質図(文献2A、2B)で具体的に見てみると、石灰岩類(limestones)、泥質岩(実際には弱い変成作用を受けて千枚岩(phyllite)やシェール(shale)となっている)、砂岩類(sandstones)などが分布しています。
詳しく見ると「アイガー」、「メンヒ」の山頂を含めたあたりも、この「ヘルベチカ系」の石灰岩類が分布しています。
一方、上記の「地質境界線」より南東側は、地質的には、第2部で説明した「外側地塊」
(external massifs)のうち、「アール地塊」(Aar massif)と呼ばれている地塊になります。
「アール地塊」は、元々は「ヨーロッパ大陸ブロック」の上部地殻を構成していた地塊であり、新生代の「アルプス造山運動」の過程で、ブロック化して大きく隆起した地塊です(文献1−2)、(文献1−3)、(文献1−4)。
「アール地塊」を構成する地質体は、原岩が原生代〜古生代前期起源と推定され、複数回の変成作用を受けた古い変成岩類である「アルトクリスタリン」(Altkristallin(独))(文献1−1)と呼ばれる変成岩類や、古生代後期の深成岩(主に花崗岩類)などからなっています。
スイスのオンライン地質図(文献2A,2B)で具体的に見てみると、「アール地塊」では、変成岩としては、片麻岩類(gneisses)、雲母片岩(mica-schist)、ミグマタイト(migmatite)、角閃岩類(amphibolites)などが分布しています。深成岩としては、古生代後期の花崗岩類(granite、grano-diorite)や閃長岩(syenite)が分布しています。注3)
なお、上記の「地質境界線」と、水平距離にして1〜2km、北西側にずれた位置に、「地形的境界線」(図3の青い線)があります。具体的には「ヴェッターホルン」の山麓部にある「グローセシャイディック峠」(Grosse sheidegg )から、「メンヒ」の山麓部にある「クライネシャイディック峠」(Kleine scheidegg)を通るラインが「地形的境界線」となっています。
このラインより南東側は、4000m級の高峰群の領域である一方で、北西側は、2000m〜2500m前後の、緩やかな高原状の地形、いわゆる「アルプ」(alp)地帯となっています。有名な「アイガー北壁」も、この「地形的境界線」の一部といえます。
この「地形的境界線」は「ユングフラウ」からさらに南西方向へ約20kmも続いていて、細長い山脈を形成しています。この山脈には、3300〜3800m級の山々が立ち並んでおり、その一部は「ブリュムスアルプ連峰」(Blüemlis-alp(独))とも呼ばれています(文献7)。また北東方向へもマイリンゲン(Meiringen)の町まで、谷状地形として続いています。(写真1)もご参照ください。
この「地形的境界線」は、(文献2A)のテクトニクス図面(“tectonic 500” レイヤー)を見ると、スラスト断層が走っているラインに、ほぼ対応しています。
つまり、このラインを境に、南東側は「アール地塊」の隆起ゾーンであり、その上部は強い浸食作用を受けて、元々はあったかもしれない「ヘルベチカ系地質グループ」の地質体が失われた、とも考えられます。
また「ヴェッターホルン」の地質構造説明(文献1−4)や、上記のスラスト断層の存在から見ると、「アール地塊」上部に元々あった「ヘルベチカ系」地質グループの地質体の一部が、全体として「ナップ」となって北西側へと滑り落ちるように移動した、とも解釈できます。
上記の「地質境界線」(図3の赤い線)の北西側は、地質的には「ヘルベチカ系」地質グループ(the Helvetic nappe system)(文献1−3)の分布域で、中生代(主に「ジュラ紀」、一部は「白亜紀」)の堆積物層と、それが部分的に変成作用を受けた地質体からなります。
スイスのオンライン地質図(文献2A、2B)で具体的に見てみると、石灰岩類(limestones)、泥質岩(実際には弱い変成作用を受けて千枚岩(phyllite)やシェール(shale)となっている)、砂岩類(sandstones)などが分布しています。
詳しく見ると「アイガー」、「メンヒ」の山頂を含めたあたりも、この「ヘルベチカ系」の石灰岩類が分布しています。
一方、上記の「地質境界線」より南東側は、地質的には、第2部で説明した「外側地塊」
(external massifs)のうち、「アール地塊」(Aar massif)と呼ばれている地塊になります。
「アール地塊」は、元々は「ヨーロッパ大陸ブロック」の上部地殻を構成していた地塊であり、新生代の「アルプス造山運動」の過程で、ブロック化して大きく隆起した地塊です(文献1−2)、(文献1−3)、(文献1−4)。
「アール地塊」を構成する地質体は、原岩が原生代〜古生代前期起源と推定され、複数回の変成作用を受けた古い変成岩類である「アルトクリスタリン」(Altkristallin(独))(文献1−1)と呼ばれる変成岩類や、古生代後期の深成岩(主に花崗岩類)などからなっています。
スイスのオンライン地質図(文献2A,2B)で具体的に見てみると、「アール地塊」では、変成岩としては、片麻岩類(gneisses)、雲母片岩(mica-schist)、ミグマタイト(migmatite)、角閃岩類(amphibolites)などが分布しています。深成岩としては、古生代後期の花崗岩類(granite、grano-diorite)や閃長岩(syenite)が分布しています。注3)
なお、上記の「地質境界線」と、水平距離にして1〜2km、北西側にずれた位置に、「地形的境界線」(図3の青い線)があります。具体的には「ヴェッターホルン」の山麓部にある「グローセシャイディック峠」(Grosse sheidegg )から、「メンヒ」の山麓部にある「クライネシャイディック峠」(Kleine scheidegg)を通るラインが「地形的境界線」となっています。
このラインより南東側は、4000m級の高峰群の領域である一方で、北西側は、2000m〜2500m前後の、緩やかな高原状の地形、いわゆる「アルプ」(alp)地帯となっています。有名な「アイガー北壁」も、この「地形的境界線」の一部といえます。
この「地形的境界線」は「ユングフラウ」からさらに南西方向へ約20kmも続いていて、細長い山脈を形成しています。この山脈には、3300〜3800m級の山々が立ち並んでおり、その一部は「ブリュムスアルプ連峰」(Blüemlis-alp(独))とも呼ばれています(文献7)。また北東方向へもマイリンゲン(Meiringen)の町まで、谷状地形として続いています。(写真1)もご参照ください。
この「地形的境界線」は、(文献2A)のテクトニクス図面(“tectonic 500” レイヤー)を見ると、スラスト断層が走っているラインに、ほぼ対応しています。
つまり、このラインを境に、南東側は「アール地塊」の隆起ゾーンであり、その上部は強い浸食作用を受けて、元々はあったかもしれない「ヘルベチカ系地質グループ」の地質体が失われた、とも考えられます。
また「ヴェッターホルン」の地質構造説明(文献1−4)や、上記のスラスト断層の存在から見ると、「アール地塊」上部に元々あった「ヘルベチカ系」地質グループの地質体の一部が、全体として「ナップ」となって北西側へと滑り落ちるように移動した、とも解釈できます。
5−1章―(2)節 「アイガー」(Eiger)の地質
「アイガー」(Eiger;3967m)は、1500mにも及ぶ巨大な絶壁である「アイガー北壁」(Eiger nordwand)で良く知られています。特に麓の「グリンデルワルド」から望むと、目がくらむような絶壁で、見ているだけで圧倒されます(写真2)。「アイガー」の標高は4000mにわずか数十m足りませんが、「ベルナーオーバーラント三山」のうちでは最も難関の山で、かつ「ベルナーオーバーラント山群」のうち最も印象的な山容をした山です(文献4)、(文献6)、(文献9)。
さて「アイガー」の地質ですが、スイスのオンライン地質図(文献2A、2B)で詳しく見ると、前述の「地質境界線」が、山頂部よりやや南東側を通っていることから、「アイガー北壁」や山頂部は、「ヘルベチカ系」地質グループに属する、「ジュラ紀」〜「白亜紀」に堆積した石灰岩類(limestones)からなっています。ここの石灰岩自体は本来、かなり硬い岩ですが、氷河に削られて垂直に近い絶壁となっているため、しばしば、この石灰岩の落石が起き、その為に「アイガー北壁」が登攀困難な「死の絶壁」とも呼ばれる所以です(文献9)。「アイガー北壁」を形成している石灰岩類は、北壁の末端部を通る「アイガートレイル」を歩くと、大量の崖錐堆積物として観察することができます。
また、アイガーの頂上や、頂上から北東方向に長く伸びる切り立った山稜である「アイガー東山稜」(ミッテルレギ稜;Mittellegi Grate)も、「アイガー北壁」と同様に石灰岩類からなっています。さらに、アイガーの山体内部を通る登山電車のルートは、この石灰岩類を繰り抜いて作られており、トンネルの内側も石灰岩類であることが観察できます(写真5)。
ところで前述の「アイガートレイル」は、「アイガー北壁」の直下を歩く、人気のハイキングコースです。コース上は、「アイガー北壁」から落ちてきた石灰岩の岩屑が溜まった崖錐となっており、転石もほとんど石灰岩ですが、地質図(文献2A)で詳しく見ると、トレイル自体の地質は、「石灰岩」類以外に、「ノースヘルベチカ系フリッシュ」(the North Helvetic Flysch)と呼ばれる、フリッシュ性堆積物(泥岩、砂岩類)も分布しています。
この地質体は、新生代の「アルプス造山運動」のうち「古第三紀」に、隆起により出来つつあった山地から、浸食によって山麓部(海底扇状地あるいは陸上扇状地)に運ばれて堆積した破砕性堆積物です。(文献2A)によると、堆積時代は、古第三紀のうち、「始新世」末の「ブリアボリアン期」〜「漸新世」初頭の「ルベリアン期」(約38〜28Ma=約0.4〜0.3億年前)です。
アイガーの山頂部や北壁を形成している石灰岩類の形成年代が「ジュラ紀」後期〜「白亜紀」初頭(約1.6〜1.4億年前)であるのと比べると、地質体としてはかなりの新参者です。一方で「アルプス造山運動」の直接的な証拠物件、とも言えるでしょう。
さて「アイガー」の地質ですが、スイスのオンライン地質図(文献2A、2B)で詳しく見ると、前述の「地質境界線」が、山頂部よりやや南東側を通っていることから、「アイガー北壁」や山頂部は、「ヘルベチカ系」地質グループに属する、「ジュラ紀」〜「白亜紀」に堆積した石灰岩類(limestones)からなっています。ここの石灰岩自体は本来、かなり硬い岩ですが、氷河に削られて垂直に近い絶壁となっているため、しばしば、この石灰岩の落石が起き、その為に「アイガー北壁」が登攀困難な「死の絶壁」とも呼ばれる所以です(文献9)。「アイガー北壁」を形成している石灰岩類は、北壁の末端部を通る「アイガートレイル」を歩くと、大量の崖錐堆積物として観察することができます。
また、アイガーの頂上や、頂上から北東方向に長く伸びる切り立った山稜である「アイガー東山稜」(ミッテルレギ稜;Mittellegi Grate)も、「アイガー北壁」と同様に石灰岩類からなっています。さらに、アイガーの山体内部を通る登山電車のルートは、この石灰岩類を繰り抜いて作られており、トンネルの内側も石灰岩類であることが観察できます(写真5)。
ところで前述の「アイガートレイル」は、「アイガー北壁」の直下を歩く、人気のハイキングコースです。コース上は、「アイガー北壁」から落ちてきた石灰岩の岩屑が溜まった崖錐となっており、転石もほとんど石灰岩ですが、地質図(文献2A)で詳しく見ると、トレイル自体の地質は、「石灰岩」類以外に、「ノースヘルベチカ系フリッシュ」(the North Helvetic Flysch)と呼ばれる、フリッシュ性堆積物(泥岩、砂岩類)も分布しています。
この地質体は、新生代の「アルプス造山運動」のうち「古第三紀」に、隆起により出来つつあった山地から、浸食によって山麓部(海底扇状地あるいは陸上扇状地)に運ばれて堆積した破砕性堆積物です。(文献2A)によると、堆積時代は、古第三紀のうち、「始新世」末の「ブリアボリアン期」〜「漸新世」初頭の「ルベリアン期」(約38〜28Ma=約0.4〜0.3億年前)です。
アイガーの山頂部や北壁を形成している石灰岩類の形成年代が「ジュラ紀」後期〜「白亜紀」初頭(約1.6〜1.4億年前)であるのと比べると、地質体としてはかなりの新参者です。一方で「アルプス造山運動」の直接的な証拠物件、とも言えるでしょう。
5−1章―(3)節 「ユングフラウ」(Jungfrau)、「メンヒ」(Mönch)の地質
「ユングフラウ」(Jungfrau;4158m)(文献10)と、「メンヒ」(Mönch;4110m)(文献11)は、4100m台の高さを誇り、「アイガー」と共に、「ベルナーオーバーラント三山」を構成する高峰です。登山電車にて、両者の中間コルにある、「ユングフラウヨッホ」駅(Jungfrau joch;約3450m)まで容易にアクセスできるため、両者とも麓から日帰りでも登れる4000m峰です(文献6)、(文献10)、(文献11)。
この節では、この2つの山の地質をまとめて説明します。
さて、この2つの山の地質ですが、前記の「地質境界線」が、その山体を通っている為、この2つの山の地質は、いわゆる「アルトクリスタリン」(Altkristallin)と呼ばれる古い変成岩類(一部、古生代の深成岩も含む)と、「アイガー」と同じ、「ヘルベチカ系」地質グループに属する、ジュラ紀の「石灰岩類」との、2種類の地質体からなっています。図3,図5もご参照ください。
3―A項) 「ユングフラウ」
まず「ユングフラウ」の地質から説明します。スイスのオンライン地質図(文献2B)によると「ユングフラウ」の山頂付近や一般登山ルート沿いは、「アルトクリスタリン」グループに属する、片麻岩類(gneisses)からなっています(図5)。
「ユングフラウ」の山頂部は、北のユングフラウヨッホあたりから眺めると、東側へ傾斜した層状の構造が認められます(写真3)。このあたりは上記の通り、片麻岩などの変成岩分布域なので、堆積岩の層構造ではありません。この層状構造ができたメカニズムは不明です。
一方、山体の北西側、「ラウターブルンネン」(Lauter brunnen)の谷に面した斜面(「シュバルツメンヒ」(Schwarz monch)呼ばれている岩峰)(写真4)や、西側、北側の中腹部は、「メンヒ」から続く、「ヘルベチカ系」地質グループに属する堆積岩の分布域で、主にはジュラ紀の石灰岩類(「クインテン石灰岩」;the Quintenn limestone)からなり、その他 白亜紀の石灰岩類、泥質岩類(主に千枚岩;phyllite)も一部含まれています(図5)。
このあたり、見た目は黒っぽいゴツゴツした岩相で、あまり石灰岩類の感じはしませんが、ミューレンあたりからよく見ると、いかにも堆積岩らしい層状構造が認められます(写真4)。
3−B項) 「メンヒ」
次に「メンヒ」の地質について説明します。山頂付近の地質は、(文献2A)では、「アルトクリスタリン」グループに属する古い変成岩類(主に片麻岩類;(geisses))となっています(図5)。なお(文献2B)では花崗岩類(granites)と書かれていますが、おそらく記載ミスと思われます。
「メンヒ」の一般的な登山ルートは、「オーバーメンヒヨッホ」(Obers Monchs-joch)と呼ばれるコル付近から登る南東稜ですが、南東稜の基部付近と、「グリンデルワルド」に面した山体の中腹部は、「アイガー」から続く「ヘルベチカ系」地質グループに属する、ジュラ紀の石灰岩類が、局所的に分布しており、このあたり、両グループの地質体が入り混じっているようです。
筆者は、南東稜から「メンヒ」に登ったことがありますが、途中に数か所、岩場がありました。その時の写真を改めて見ると、南東稜の下部は黒っぽい岩で、地質図によると中生代の石灰岩、南東稜の中部は赤茶けた岩で、地質図によると片麻岩類、どちらもゴツゴツした感じの硬い岩でした(写真6)、(写真7)。
3−C項) ユングフラウヨッホ付近
次に、観光客、ハイカーも多く訪れる、「ユングフラウヨッホ」(駅)(Jungfrau joch;約3500m)付近の地質を説明します(図5)。登山電車の終着駅は、スフィンクス岩峰(Sphinx;3571m)という小さな岩峰の地下に作られています。スフィンクス岩峰は、小さいながら氷食尖峰であり、外側から見ると、いかにも硬そうな岩でできています(写真8)。
地質的には(文献2A)によると、大部分が「片麻岩類」(gneis(独))、「ミグマタイト」(migmatite(独))、「角閃岩」(amphibolit(独))からなる、とされています。なお(文献2B)では、「片麻岩類」(gneiss(英))、「花崗岩類」(granites, syenites(英))からなる、とされていて、なぜか説明に差異があります。山岳鉄道の駅や展望台もあり、詳しく調べられているはずの岩峰ですが、複雑な変成作用を受けた岩石なので、解釈が難しいのかも知れません。
(写真8)に実際のスフィンクス岩峰」の外観を示しますが、改めて見ると、下から順に、ライトグレーの岩石層、黒っぽく層状構造を持つ岩石層、やや茶色っぽく多少の層構造を持つ岩石層の、計3つの地質体からなっているように見えます。
これらは全て「アール地塊」を構成している岩石ですが、小さな岩峰でも複数の地質体からなっていることは、「アール地塊」が複雑な地史を持ち、多種多様な地質体からなっていることを示している、良い観察ポイントと言えましょう。
この節では、この2つの山の地質をまとめて説明します。
さて、この2つの山の地質ですが、前記の「地質境界線」が、その山体を通っている為、この2つの山の地質は、いわゆる「アルトクリスタリン」(Altkristallin)と呼ばれる古い変成岩類(一部、古生代の深成岩も含む)と、「アイガー」と同じ、「ヘルベチカ系」地質グループに属する、ジュラ紀の「石灰岩類」との、2種類の地質体からなっています。図3,図5もご参照ください。
3―A項) 「ユングフラウ」
まず「ユングフラウ」の地質から説明します。スイスのオンライン地質図(文献2B)によると「ユングフラウ」の山頂付近や一般登山ルート沿いは、「アルトクリスタリン」グループに属する、片麻岩類(gneisses)からなっています(図5)。
「ユングフラウ」の山頂部は、北のユングフラウヨッホあたりから眺めると、東側へ傾斜した層状の構造が認められます(写真3)。このあたりは上記の通り、片麻岩などの変成岩分布域なので、堆積岩の層構造ではありません。この層状構造ができたメカニズムは不明です。
一方、山体の北西側、「ラウターブルンネン」(Lauter brunnen)の谷に面した斜面(「シュバルツメンヒ」(Schwarz monch)呼ばれている岩峰)(写真4)や、西側、北側の中腹部は、「メンヒ」から続く、「ヘルベチカ系」地質グループに属する堆積岩の分布域で、主にはジュラ紀の石灰岩類(「クインテン石灰岩」;the Quintenn limestone)からなり、その他 白亜紀の石灰岩類、泥質岩類(主に千枚岩;phyllite)も一部含まれています(図5)。
このあたり、見た目は黒っぽいゴツゴツした岩相で、あまり石灰岩類の感じはしませんが、ミューレンあたりからよく見ると、いかにも堆積岩らしい層状構造が認められます(写真4)。
3−B項) 「メンヒ」
次に「メンヒ」の地質について説明します。山頂付近の地質は、(文献2A)では、「アルトクリスタリン」グループに属する古い変成岩類(主に片麻岩類;(geisses))となっています(図5)。なお(文献2B)では花崗岩類(granites)と書かれていますが、おそらく記載ミスと思われます。
「メンヒ」の一般的な登山ルートは、「オーバーメンヒヨッホ」(Obers Monchs-joch)と呼ばれるコル付近から登る南東稜ですが、南東稜の基部付近と、「グリンデルワルド」に面した山体の中腹部は、「アイガー」から続く「ヘルベチカ系」地質グループに属する、ジュラ紀の石灰岩類が、局所的に分布しており、このあたり、両グループの地質体が入り混じっているようです。
筆者は、南東稜から「メンヒ」に登ったことがありますが、途中に数か所、岩場がありました。その時の写真を改めて見ると、南東稜の下部は黒っぽい岩で、地質図によると中生代の石灰岩、南東稜の中部は赤茶けた岩で、地質図によると片麻岩類、どちらもゴツゴツした感じの硬い岩でした(写真6)、(写真7)。
3−C項) ユングフラウヨッホ付近
次に、観光客、ハイカーも多く訪れる、「ユングフラウヨッホ」(駅)(Jungfrau joch;約3500m)付近の地質を説明します(図5)。登山電車の終着駅は、スフィンクス岩峰(Sphinx;3571m)という小さな岩峰の地下に作られています。スフィンクス岩峰は、小さいながら氷食尖峰であり、外側から見ると、いかにも硬そうな岩でできています(写真8)。
地質的には(文献2A)によると、大部分が「片麻岩類」(gneis(独))、「ミグマタイト」(migmatite(独))、「角閃岩」(amphibolit(独))からなる、とされています。なお(文献2B)では、「片麻岩類」(gneiss(英))、「花崗岩類」(granites, syenites(英))からなる、とされていて、なぜか説明に差異があります。山岳鉄道の駅や展望台もあり、詳しく調べられているはずの岩峰ですが、複雑な変成作用を受けた岩石なので、解釈が難しいのかも知れません。
(写真8)に実際のスフィンクス岩峰」の外観を示しますが、改めて見ると、下から順に、ライトグレーの岩石層、黒っぽく層状構造を持つ岩石層、やや茶色っぽく多少の層構造を持つ岩石層の、計3つの地質体からなっているように見えます。
これらは全て「アール地塊」を構成している岩石ですが、小さな岩峰でも複数の地質体からなっていることは、「アール地塊」が複雑な地史を持ち、多種多様な地質体からなっていることを示している、良い観察ポイントと言えましょう。
5−1章―第(4)節 「ヴェッターホルン」(Wetterhorn)とその周辺の地質
「ヴェッターホルン」(Wetterhorn;3690m)(文献12)は、麓の「グリンデルワルド」の街中から見ると、その北東側に大きい山体を誇示している印象的な山です。標高は4000mには達していませんが、巨大な岩峰群が林立する山頂部は、荘厳なゴシック建築のようにも見え、この山も「ベルナーオーバーラント山群」を代表する山と言えます(写真9)。
さて、「ヴェッターホルン」の地質ですが、基本的には、前の各節で説明した、「ベルナーオーバーラント三山」と類似しています。
スイスのオンライン地質図(文献2A,2B)によると(図6)、山頂部(最高点)や山体の北西側は、「ヘルベチカ系」地質グループに属する、「ジュラ紀」や「白亜紀」の石灰岩類
(limestons)から構成されており、一部には「トリアス紀」の石灰岩類も分布しています。一方、山体の南東側は、(文献2B)では、「花崗岩類」(granites, syenites)とされていますが、(文献2A)では、片麻岩類(gneiss(独))やミグマタイト(migmatite(独))とされ、ちょっと解釈に違いがあります。
ところで「ヴェッターホルン」の西側は、標高差1500mほどの急峻な絶壁となっており、その直下にある「グローセシャイディック峠」(Grosse Scheidegg;1962 m)へと落ち込んでいます(図6)。この「グローセシャイディック峠」は、地形的には、氷河の浸食作用によって削られたという側面もあると思われますが、地質学的には、(文献2A)のうち、テクトニックマップで詳しく見ると、この峠を通るスラスト断層が示されており、断層によって、絶壁の大きな落差が形成されたという面が大きいようです。
またグリンデルワルドから望むと、ヴェッターホルンの中腹に石灰岩層が大きく褶曲した構造が見えます(写真10)。「アルプス造山運動」に伴う大きな力が加わった様子が、良く解ります。
さて、「ヴェッターホルン」の地質ですが、基本的には、前の各節で説明した、「ベルナーオーバーラント三山」と類似しています。
スイスのオンライン地質図(文献2A,2B)によると(図6)、山頂部(最高点)や山体の北西側は、「ヘルベチカ系」地質グループに属する、「ジュラ紀」や「白亜紀」の石灰岩類
(limestons)から構成されており、一部には「トリアス紀」の石灰岩類も分布しています。一方、山体の南東側は、(文献2B)では、「花崗岩類」(granites, syenites)とされていますが、(文献2A)では、片麻岩類(gneiss(独))やミグマタイト(migmatite(独))とされ、ちょっと解釈に違いがあります。
ところで「ヴェッターホルン」の西側は、標高差1500mほどの急峻な絶壁となっており、その直下にある「グローセシャイディック峠」(Grosse Scheidegg;1962 m)へと落ち込んでいます(図6)。この「グローセシャイディック峠」は、地形的には、氷河の浸食作用によって削られたという側面もあると思われますが、地質学的には、(文献2A)のうち、テクトニックマップで詳しく見ると、この峠を通るスラスト断層が示されており、断層によって、絶壁の大きな落差が形成されたという面が大きいようです。
またグリンデルワルドから望むと、ヴェッターホルンの中腹に石灰岩層が大きく褶曲した構造が見えます(写真10)。「アルプス造山運動」に伴う大きな力が加わった様子が、良く解ります。
5−1章―(5)節 「グリンデルワルド」周辺の地質
「グリンデルワルド」の周辺は、標高が2000m前後の高原状の地帯(いわゆる「アルプ」;“alp”)となっており、前記の「ベルナーオーバーラント三山」を望むような、ハイキングコースが多数あります。例えば、北側にはフィルスト(First)を起点としたハイキングコース、南西側には、クライネシャイディック(Kline Scheidegg)やメンリッヘン
(Mennlichen)を起点としたハイキングコースがあります。また、「グリンデルワルド」の谷とは少し離れた、「ラウターブルンネン」(Lauter Brunnen)の谷沿いにも、シルトホルン(Silthorn;2969m)やミューレン(Murren)を中心としたハイキングコースがあります。図2もご参照ください。
この付近の地質を、スイスのオンライン地質図(文献2B)によって見てみると、大部分が「ジュラ紀」の泥質岩類からなっています(図3,図6,図9)。実際には、弱い変成作用を受け、千枚岩(phyllite)やシェール(shale)となっている感じです。実際、この辺りを歩いて露頭を見てみると、層状の構造がはっきりしており、千枚岩やシェールと思われます(写真11)、(写真13)、(写真14)。一方、石灰岩的な岩石もあり(写真12)、泥質成分と石灰質成分が時代ごとに複雑に堆積したことを伺わせます。なお地質グループとしては全て、「ヘルベチカ系」地質グループに属します。
ところで、グリンデルワルドの谷から山を一つ越えた場所に、大きな氷食谷である「ラウターブルンネン」(Lauterbrunnen)の谷があります。この谷は、両側の側面が、比高300mほどの絶壁となっており、そこから、落差が200〜300mもある滝が何本も流れ落ちている、面白い地形となっています(写真17)。
この谷の部分の地質を、(文献2A、2B)で確認すると、この絶壁部分は、ジュラ紀の石灰岩類(「クインテン石灰岩」;Quinten limestone)でできています(図9)。
この絶壁をよく見ると、堆積による層構造が解りますが、全体がキレイな成層構造をしているわけではなく、断層がいくつも走っており、場所によっては断層によってブロック化している感じです(写真18)。
「ラウターブルンネン」の谷は、氷食谷であるのは明らかですが、断面が緩やかな「U字」の、典型的な「U字谷」ではなく、断面が「箱型」になっていて、地形的にはちょっと変わっています(写真15)。これはおそらく、全体が石灰岩類からできている為に、氷河による削られ方が独特だったのでは、と思います(この段落は私見です)。
(Mennlichen)を起点としたハイキングコースがあります。また、「グリンデルワルド」の谷とは少し離れた、「ラウターブルンネン」(Lauter Brunnen)の谷沿いにも、シルトホルン(Silthorn;2969m)やミューレン(Murren)を中心としたハイキングコースがあります。図2もご参照ください。
この付近の地質を、スイスのオンライン地質図(文献2B)によって見てみると、大部分が「ジュラ紀」の泥質岩類からなっています(図3,図6,図9)。実際には、弱い変成作用を受け、千枚岩(phyllite)やシェール(shale)となっている感じです。実際、この辺りを歩いて露頭を見てみると、層状の構造がはっきりしており、千枚岩やシェールと思われます(写真11)、(写真13)、(写真14)。一方、石灰岩的な岩石もあり(写真12)、泥質成分と石灰質成分が時代ごとに複雑に堆積したことを伺わせます。なお地質グループとしては全て、「ヘルベチカ系」地質グループに属します。
ところで、グリンデルワルドの谷から山を一つ越えた場所に、大きな氷食谷である「ラウターブルンネン」(Lauterbrunnen)の谷があります。この谷は、両側の側面が、比高300mほどの絶壁となっており、そこから、落差が200〜300mもある滝が何本も流れ落ちている、面白い地形となっています(写真17)。
この谷の部分の地質を、(文献2A、2B)で確認すると、この絶壁部分は、ジュラ紀の石灰岩類(「クインテン石灰岩」;Quinten limestone)でできています(図9)。
この絶壁をよく見ると、堆積による層構造が解りますが、全体がキレイな成層構造をしているわけではなく、断層がいくつも走っており、場所によっては断層によってブロック化している感じです(写真18)。
「ラウターブルンネン」の谷は、氷食谷であるのは明らかですが、断面が緩やかな「U字」の、典型的な「U字谷」ではなく、断面が「箱型」になっていて、地形的にはちょっと変わっています(写真15)。これはおそらく、全体が石灰岩類からできている為に、氷河による削られ方が独特だったのでは、と思います(この段落は私見です)。
5−1章―(6)節 「ベルナーオーバーラント山群」奥地の山々の地質
「ベルナーオーバーラント山群」のうち、上記の「ベルナーオーバーラント三山」は、グリンデルワルド」の街や、アルプ地帯のハイキングコースからも良く眺められますが、実際にはその更に奥に、4000m級の高峰群が多数あります(図2)、(図7)、(写真11)。
具体的には、この山群最高峰の「フィンスターアールホルン(Finsteraarhorn;4274m)を筆頭に、「シュレックホルン」(Schreckhorn;4078m)、「ラウターアールホルン」
(Lauteraarhorn;4042m)、「フィッシャーホルン」(Fischer horn;4049m)、「グリュンホルン」(Grunhorn:4043m)、「アレッチホルン」(Aletschhorn;4194m)などが挙げられ、どの山も氷河によって削られて、鋭い姿の氷食尖峰となっています(図7)。
これらの山々は、奥地にあってアクセスに時間がかかることや、険しくてクライミング要素が強い山々なので、観光客やハイカーが行けるような場所ではなく、実力のあるクライマーのみが行ける場所ですが、フィルスト(First)などのグリンデルワルド近郊の展望台からその一部が望め、印象的な山々ばかりです。なおこの奥地で、アイゼン程度の装備で一般登山者が歩けるのは、この山群を貫く、「アレッチ氷河」(the Aletsch glacier)を歩く氷河歩きルートくらいです。
さて、これら奥山の地質を、スイスのオンライン地質図(文献2A、2B)によって確認します。このあたりは全て、基盤岩体が隆起して地表に現れた「アール地塊」に属します。
地質的には、古い変成岩類である「アルトクリスタリン」類、具体的には片麻岩類(gneiss)、雲母片岩(mica-schist)、角閃岩類(amphibolites)などで構成されています。
上記の4000m級の高峰群の多くが、山頂部は片麻岩類からなっていますが、この山群最高峰の「フィンスターアールホルン」と、それに隣接する「グリュンホルン」(Grunhorn)は、山頂部が角閃岩類となっています(図8)。
(文献5)によると、「グリュンホルン」(※ ドイツ語の ”grun”は、英語の”green”と同義で、「緑色」の意)は、日差しが当たると角閃岩が(深)緑色っぽく見えることから名付けられた、とのことです。
「ベルナーオーバーラント山群」のうち南東部、「アレッチ氷河」の中流から下流域の周辺は、標高がやや下がり、3500〜3000m級の山々が連なっていますが、地質図(文献2A,2B)でよく見ると、この辺りは、「アール地塊」の一部ではありますが、「アルトクリスタリン」に属する変成岩類ではなく、それら変成岩へと貫入した花崗岩類(granites,
grano-diorites)が広く分布しています。(文献1―1)、(文献2B)によると、その花崗岩類の形成年代は、約300Ma(石炭紀末)頃です。
本連載の第2―2章で説明しましたが、古生代の後期、「石炭紀」〜「ペルム紀」にかけては、「ヴァリスカン造山運動」の最盛期より少し後の時代で、「ポスト・ヴァリスカン期」(post-Variscan)と呼ばれています。この時代、「アルプス地域」やその周辺では火成活動が活発で、例えば「モンブラン山群」に広く分布している花崗岩類も、この時代の産物です。上記の「アール地塊」南東部に分布している花崗岩類も、このような広域的なテクトニクス的環境で形成された深成岩と思われます。
具体的には、この山群最高峰の「フィンスターアールホルン(Finsteraarhorn;4274m)を筆頭に、「シュレックホルン」(Schreckhorn;4078m)、「ラウターアールホルン」
(Lauteraarhorn;4042m)、「フィッシャーホルン」(Fischer horn;4049m)、「グリュンホルン」(Grunhorn:4043m)、「アレッチホルン」(Aletschhorn;4194m)などが挙げられ、どの山も氷河によって削られて、鋭い姿の氷食尖峰となっています(図7)。
これらの山々は、奥地にあってアクセスに時間がかかることや、険しくてクライミング要素が強い山々なので、観光客やハイカーが行けるような場所ではなく、実力のあるクライマーのみが行ける場所ですが、フィルスト(First)などのグリンデルワルド近郊の展望台からその一部が望め、印象的な山々ばかりです。なおこの奥地で、アイゼン程度の装備で一般登山者が歩けるのは、この山群を貫く、「アレッチ氷河」(the Aletsch glacier)を歩く氷河歩きルートくらいです。
さて、これら奥山の地質を、スイスのオンライン地質図(文献2A、2B)によって確認します。このあたりは全て、基盤岩体が隆起して地表に現れた「アール地塊」に属します。
地質的には、古い変成岩類である「アルトクリスタリン」類、具体的には片麻岩類(gneiss)、雲母片岩(mica-schist)、角閃岩類(amphibolites)などで構成されています。
上記の4000m級の高峰群の多くが、山頂部は片麻岩類からなっていますが、この山群最高峰の「フィンスターアールホルン」と、それに隣接する「グリュンホルン」(Grunhorn)は、山頂部が角閃岩類となっています(図8)。
(文献5)によると、「グリュンホルン」(※ ドイツ語の ”grun”は、英語の”green”と同義で、「緑色」の意)は、日差しが当たると角閃岩が(深)緑色っぽく見えることから名付けられた、とのことです。
「ベルナーオーバーラント山群」のうち南東部、「アレッチ氷河」の中流から下流域の周辺は、標高がやや下がり、3500〜3000m級の山々が連なっていますが、地質図(文献2A,2B)でよく見ると、この辺りは、「アール地塊」の一部ではありますが、「アルトクリスタリン」に属する変成岩類ではなく、それら変成岩へと貫入した花崗岩類(granites,
grano-diorites)が広く分布しています。(文献1―1)、(文献2B)によると、その花崗岩類の形成年代は、約300Ma(石炭紀末)頃です。
本連載の第2―2章で説明しましたが、古生代の後期、「石炭紀」〜「ペルム紀」にかけては、「ヴァリスカン造山運動」の最盛期より少し後の時代で、「ポスト・ヴァリスカン期」(post-Variscan)と呼ばれています。この時代、「アルプス地域」やその周辺では火成活動が活発で、例えば「モンブラン山群」に広く分布している花崗岩類も、この時代の産物です。上記の「アール地塊」南東部に分布している花崗岩類も、このような広域的なテクトニクス的環境で形成された深成岩と思われます。
【他の連載へのリンク】
この連載の各項目へのリンクがあります
一つ前の連載へのリンクです
次の連載へのリンクです(現在、内容修正中)
【注釈の項】
注1) 山々の標高について
この章で記載した山々などの標高は、スイスのオンライン地図(文献2A)のうち、地形図レイヤーの値を採用し、記載しています。文献、ガイドブックなどによっては、数m程度違う値となっている場合があります。
注2) スイスのオンライン地質図について
スイスのオンライン地質図は、パソコン等で見る「ウエブ版」(文献2A)と、スマホのアプリとなっている「アプリ版」(文献2B)(アプリ名;“Swiss topo”)とがあります。
どちらも(Swiss topo)という機関がデータ元ですが、「ウエブ版」(文献2A)は、ポップアップの地質解説がドイツ語なのでちょっと解りにくく、「アプリ版」(文献2B)は、地質解説が英語で解りやすい、という違いがあります。
また細かく見ると、地質説明や地質分布図にも、少し違いがあります。
この章では、それぞれの山、地域の、地質(岩石)名称は、英語名称が使われている「アプリ版」(文献2B)を主に引用しましたが、より説明が詳しい「ウエブ版」(文献2A)も参照しました。
注3) 岩石の説明
この章では、色々な岩石名が出てきますが、それらを以下に説明しておきます。詳しくは(文献13)などをご参照ください。
・「片麻岩」類(gneisses): 変成岩のうち、見た目が濃い色(黒っぽい)の部分と、淡い色(白っぽい)の部分が縞模様(片麻状組織)となっている岩石。どちらかというと、高温型の変成岩。日本では分布が限定的だが、ヨーロッパアルプスや世界各地の造山帯、古い地塊(クラトン)では良く見られる。
元となった岩石や、含まれる鉱物によって、細かく種類が分けられている。
原岩が花崗岩類(深成岩)と推定されるものは、「正片麻岩」(ortho-gneiss)、原岩が堆積岩(泥岩、砂岩など)と推定されるものは、「パラ片麻岩」(「準片麻岩」とも)(para-gneiss)という、2種類に区分するやり方も良く使われる。
・「ミグマタイト」(migmatite); 変成岩のうち、片麻岩がさらに高温化にさらされ、部分的に融解したのち、再び固まった変成岩。見た目は様々で、片麻岩との明確な区別は難しい。溶融度が大きいと、再結晶した鉱物が目立ち、深成岩のように見える。
スイスのオンライン地質図では、例えば「ミグマタイト的な片麻岩」
(Gneis-migmatitisch(独))といった書き方が良く見られる。
・「雲母片岩」(mica-schist); 変成岩のうち、「結晶片岩」類の一つ。結晶片岩類は「片理構造」と呼ばれる、ペラペラしたシートが重なったような構造をもつが、その中に雲母(mica)が多く含まれるものを雲母片岩と呼ぶ。
「結晶片岩」類は、多くの名称があって、文献によって同じものが別の名前で呼ばれることもあるが、(文献13)では、「白雲母片岩」(muscovite-schist)として記載されている。日本では「泥質片岩」や「黒色片岩」と呼ばれる結晶片岩類も、白雲母が多く含まれることが多いので、「雲母片岩」と同類と言える。
・「角閃岩」類(amphibolites); 変成岩のうち、「角閃石」(類)と呼ばれる鉱物が多い変成岩。見た目はかなり黒っぽく、風化した表面はやや緑色を帯びる。原岩は、玄武岩などの苦鉄質の火成岩で、海洋プレート沈み込み帯で、海洋プレート上部の玄武岩、ハンレイ岩が地下深部で変成作用を受けたものが多い、と解釈されている。なお岩石としての「角閃岩」も、鉱物としての「角閃石」も、細かく言うと単一の名称ではなく、元素組成によって多数の種類に分類される。
・「千枚岩」(phyllite); 原岩は泥質岩で、中程度の変成作用受け、厚さ数mmの、ペラペラしたシート状の構造をもつ。色はダークグレー〜黒色。
・「スレート」(slate); 日本語では「粘板岩」とも呼ばれる。原岩は泥質岩で、「千枚岩」よりも変成度は低く、数cm程度の、板状の構造を持つ。なお日本で住宅の屋根材などとして使われる「スレート」は工業的に作ったものだが、元々、ヨーロッパなどでは、天然の「スレート」が屋根材として使われていた。
・「花崗岩」類(granites); 狭義の「花崗岩」(granite)は、マグマが地中で固まった深成岩の一種で、鉱物組成としては、石英、斜長石、カリ長石、黒雲母からなり、シリカ分が多い(=珪長質;felsic)深成岩。見た目は白色系鉱物(石英、斜長石、カリ長石)に、黒色系鉱物(黒雲母)が点在した粗粒の岩石。
類似した珪長質の深成岩で、鉱物組成、構成が多少違うものに、「花崗閃緑岩」
(grano-diorite)、「トーナル岩」(tonalite)などがあり、見た目が似ている為、まとめて「花崗岩類」と呼ぶことが多い。
・「閃長岩」(syenite); 花崗岩に似た見た目の、深成岩の一種。鉱物組成としては、カリ長石、斜長石、有色鉱物(主に輝石)が主体で、石英は少ない(5%以下)。日本ではほとんど見られない。
・「石灰岩」類(limestones); 狭義の「石灰岩」(limestone)は、化学組成が(CaCO3;炭酸カルシウム)のライトグレー〜白っぽい岩石。サンゴ、有孔虫など、海生生物の炭酸カルシウム質の殻が堆積してできたものが殆ど。「石灰岩」類(limestones)と呼ぶ場合は、Mg分が入ったドロマイト(dolomite)や、泥質成分が混じったもの(marly limestone)を含む。
変成作用を受けると結晶質となり、「大理石」(marble)と呼ばれる。
この章で記載した山々などの標高は、スイスのオンライン地図(文献2A)のうち、地形図レイヤーの値を採用し、記載しています。文献、ガイドブックなどによっては、数m程度違う値となっている場合があります。
注2) スイスのオンライン地質図について
スイスのオンライン地質図は、パソコン等で見る「ウエブ版」(文献2A)と、スマホのアプリとなっている「アプリ版」(文献2B)(アプリ名;“Swiss topo”)とがあります。
どちらも(Swiss topo)という機関がデータ元ですが、「ウエブ版」(文献2A)は、ポップアップの地質解説がドイツ語なのでちょっと解りにくく、「アプリ版」(文献2B)は、地質解説が英語で解りやすい、という違いがあります。
また細かく見ると、地質説明や地質分布図にも、少し違いがあります。
この章では、それぞれの山、地域の、地質(岩石)名称は、英語名称が使われている「アプリ版」(文献2B)を主に引用しましたが、より説明が詳しい「ウエブ版」(文献2A)も参照しました。
注3) 岩石の説明
この章では、色々な岩石名が出てきますが、それらを以下に説明しておきます。詳しくは(文献13)などをご参照ください。
・「片麻岩」類(gneisses): 変成岩のうち、見た目が濃い色(黒っぽい)の部分と、淡い色(白っぽい)の部分が縞模様(片麻状組織)となっている岩石。どちらかというと、高温型の変成岩。日本では分布が限定的だが、ヨーロッパアルプスや世界各地の造山帯、古い地塊(クラトン)では良く見られる。
元となった岩石や、含まれる鉱物によって、細かく種類が分けられている。
原岩が花崗岩類(深成岩)と推定されるものは、「正片麻岩」(ortho-gneiss)、原岩が堆積岩(泥岩、砂岩など)と推定されるものは、「パラ片麻岩」(「準片麻岩」とも)(para-gneiss)という、2種類に区分するやり方も良く使われる。
・「ミグマタイト」(migmatite); 変成岩のうち、片麻岩がさらに高温化にさらされ、部分的に融解したのち、再び固まった変成岩。見た目は様々で、片麻岩との明確な区別は難しい。溶融度が大きいと、再結晶した鉱物が目立ち、深成岩のように見える。
スイスのオンライン地質図では、例えば「ミグマタイト的な片麻岩」
(Gneis-migmatitisch(独))といった書き方が良く見られる。
・「雲母片岩」(mica-schist); 変成岩のうち、「結晶片岩」類の一つ。結晶片岩類は「片理構造」と呼ばれる、ペラペラしたシートが重なったような構造をもつが、その中に雲母(mica)が多く含まれるものを雲母片岩と呼ぶ。
「結晶片岩」類は、多くの名称があって、文献によって同じものが別の名前で呼ばれることもあるが、(文献13)では、「白雲母片岩」(muscovite-schist)として記載されている。日本では「泥質片岩」や「黒色片岩」と呼ばれる結晶片岩類も、白雲母が多く含まれることが多いので、「雲母片岩」と同類と言える。
・「角閃岩」類(amphibolites); 変成岩のうち、「角閃石」(類)と呼ばれる鉱物が多い変成岩。見た目はかなり黒っぽく、風化した表面はやや緑色を帯びる。原岩は、玄武岩などの苦鉄質の火成岩で、海洋プレート沈み込み帯で、海洋プレート上部の玄武岩、ハンレイ岩が地下深部で変成作用を受けたものが多い、と解釈されている。なお岩石としての「角閃岩」も、鉱物としての「角閃石」も、細かく言うと単一の名称ではなく、元素組成によって多数の種類に分類される。
・「千枚岩」(phyllite); 原岩は泥質岩で、中程度の変成作用受け、厚さ数mmの、ペラペラしたシート状の構造をもつ。色はダークグレー〜黒色。
・「スレート」(slate); 日本語では「粘板岩」とも呼ばれる。原岩は泥質岩で、「千枚岩」よりも変成度は低く、数cm程度の、板状の構造を持つ。なお日本で住宅の屋根材などとして使われる「スレート」は工業的に作ったものだが、元々、ヨーロッパなどでは、天然の「スレート」が屋根材として使われていた。
・「花崗岩」類(granites); 狭義の「花崗岩」(granite)は、マグマが地中で固まった深成岩の一種で、鉱物組成としては、石英、斜長石、カリ長石、黒雲母からなり、シリカ分が多い(=珪長質;felsic)深成岩。見た目は白色系鉱物(石英、斜長石、カリ長石)に、黒色系鉱物(黒雲母)が点在した粗粒の岩石。
類似した珪長質の深成岩で、鉱物組成、構成が多少違うものに、「花崗閃緑岩」
(grano-diorite)、「トーナル岩」(tonalite)などがあり、見た目が似ている為、まとめて「花崗岩類」と呼ぶことが多い。
・「閃長岩」(syenite); 花崗岩に似た見た目の、深成岩の一種。鉱物組成としては、カリ長石、斜長石、有色鉱物(主に輝石)が主体で、石英は少ない(5%以下)。日本ではほとんど見られない。
・「石灰岩」類(limestones); 狭義の「石灰岩」(limestone)は、化学組成が(CaCO3;炭酸カルシウム)のライトグレー〜白っぽい岩石。サンゴ、有孔虫など、海生生物の炭酸カルシウム質の殻が堆積してできたものが殆ど。「石灰岩」類(limestones)と呼ぶ場合は、Mg分が入ったドロマイト(dolomite)や、泥質成分が混じったもの(marly limestone)を含む。
変成作用を受けると結晶質となり、「大理石」(marble)と呼ばれる。
【参考文献】
(文献1) O. A. Pfiffner 著 “Geology of the Alps”, 2nd edition ,Wiley Blackball社刊,
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1) (文献1)のうち、2−2章の「アルトクリスタリン」に関する項
(文献1−2) (文献1)のうち、図2-6 「アール地塊の地質断面図とその説明」
(文献1−3) (文献1)のうち、6−3章「新生代造山運動」の項、
及び 図6-17 「中部アルプスの、地質断面図による進化」
(文献1−4) (文献1)のうち、5−4章「アルプスの深部構造」の項、
及び、図5-4-1 「中部アルプス 基盤岩体の隆起量」
(文献1−5) (文献1)のうち、3−1章―(1)―b項
「ヘルベチカ系」地質グループの項
(文献1−6) (文献1)のうち、5−2章―(4)項 「ヘルベチカ系」の項
及び、図5-2-9 「ヴェッターホルンの地質断面図」
(文献2A) スイスのオンライン地質図(ウエブ版)
https://map.geo.admin.ch/
※ 地質図は、メニューより、 > Geocatalog > Nature and Environment > Geology
> GeoCover Vector Datasets 、より見ることができる。
※ 断層などは、メニューより、> Geocatalog > Nature and Environment > Geology
> Tectonics 500 、より見ることができる。
※ 地形図も兼ねているので、地形図レイヤーより、山名、標高なども確認できる。
※ 地図自体は(EN)を選ぶと英語表記になるが、ポップアップの地質解説はドイツ語
なので、ちょっと解りにくい。
※ 利用したバージョンは、v 1.59.0
(文献2B) スイスのオンライン地質図(スマホアプリ版)
※ スマホに、“Swiss topo” というアプリをインストールして利用する。
※ メニューより、”geology” > “Gological Map” を選ぶと地質図を見ることができる。
※ 地図自体も、ポップアップの地質解説も全て英語なので、解りやすい。
※ 利用したバージョンは、v 1.19.1
(文献3) スイスの地質に関する解説サイト
Strati CH;Lithostratigraphic Lexicon of Switzerland
https://www.strati.ch/en/
(文献4) 「地球の歩き方;スイス(2024-2025年版)」 Gakken社 刊 (2023)
(文献5) 金原 著「ヨーロッパアルプス 登山・ハイキング 改訂2版」
本の泉社 刊 (2013)
(文献6) ハンス グロッセン(Hans Grossen)著、近藤 等 訳、
「ベルナーオーバーラント;特選100コース」 山と渓谷社 刊 (1983)
(文献7) ウイキペディア英語版の、(Bernese Alps)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernese_Alps
(2025年9月 閲覧)
(文献8) ウイキペディア英語版の、(Aletsch Glacier)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Aletsch_Glacier
(2025年9月 閲覧)
(文献9) ウイキペディア英語版の、(Eiger)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Eiger
(2025年9月 閲覧)
(文献10) ウイキペディア英語版の、(Jungfrau)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Jungfrau
(2025年9月 閲覧)
(文献11) ウイキペディア英語版の、(Mönch)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch
(2025年9月 閲覧)
(文献12) ウイキペディア英語版の、(Wetterhorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetterhorn
(2025年9月 閲覧)
(文献13) 西本 著「観察を楽しむ、特徴がわかる 岩石図鑑」
ナツメ社刊 (2020)
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1) (文献1)のうち、2−2章の「アルトクリスタリン」に関する項
(文献1−2) (文献1)のうち、図2-6 「アール地塊の地質断面図とその説明」
(文献1−3) (文献1)のうち、6−3章「新生代造山運動」の項、
及び 図6-17 「中部アルプスの、地質断面図による進化」
(文献1−4) (文献1)のうち、5−4章「アルプスの深部構造」の項、
及び、図5-4-1 「中部アルプス 基盤岩体の隆起量」
(文献1−5) (文献1)のうち、3−1章―(1)―b項
「ヘルベチカ系」地質グループの項
(文献1−6) (文献1)のうち、5−2章―(4)項 「ヘルベチカ系」の項
及び、図5-2-9 「ヴェッターホルンの地質断面図」
(文献2A) スイスのオンライン地質図(ウエブ版)
https://map.geo.admin.ch/
※ 地質図は、メニューより、 > Geocatalog > Nature and Environment > Geology
> GeoCover Vector Datasets 、より見ることができる。
※ 断層などは、メニューより、> Geocatalog > Nature and Environment > Geology
> Tectonics 500 、より見ることができる。
※ 地形図も兼ねているので、地形図レイヤーより、山名、標高なども確認できる。
※ 地図自体は(EN)を選ぶと英語表記になるが、ポップアップの地質解説はドイツ語
なので、ちょっと解りにくい。
※ 利用したバージョンは、v 1.59.0
(文献2B) スイスのオンライン地質図(スマホアプリ版)
※ スマホに、“Swiss topo” というアプリをインストールして利用する。
※ メニューより、”geology” > “Gological Map” を選ぶと地質図を見ることができる。
※ 地図自体も、ポップアップの地質解説も全て英語なので、解りやすい。
※ 利用したバージョンは、v 1.19.1
(文献3) スイスの地質に関する解説サイト
Strati CH;Lithostratigraphic Lexicon of Switzerland
https://www.strati.ch/en/
(文献4) 「地球の歩き方;スイス(2024-2025年版)」 Gakken社 刊 (2023)
(文献5) 金原 著「ヨーロッパアルプス 登山・ハイキング 改訂2版」
本の泉社 刊 (2013)
(文献6) ハンス グロッセン(Hans Grossen)著、近藤 等 訳、
「ベルナーオーバーラント;特選100コース」 山と渓谷社 刊 (1983)
(文献7) ウイキペディア英語版の、(Bernese Alps)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernese_Alps
(2025年9月 閲覧)
(文献8) ウイキペディア英語版の、(Aletsch Glacier)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Aletsch_Glacier
(2025年9月 閲覧)
(文献9) ウイキペディア英語版の、(Eiger)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Eiger
(2025年9月 閲覧)
(文献10) ウイキペディア英語版の、(Jungfrau)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Jungfrau
(2025年9月 閲覧)
(文献11) ウイキペディア英語版の、(Mönch)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nch
(2025年9月 閲覧)
(文献12) ウイキペディア英語版の、(Wetterhorn)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetterhorn
(2025年9月 閲覧)
(文献13) 西本 著「観察を楽しむ、特徴がわかる 岩石図鑑」
ナツメ社刊 (2020)
【書記事項】
初版リリース;2025年9月21日
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
ベルクハイルさんの記事一覧
※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
どなたでも、山に関する知識や技術などのノウハウを簡単に残して共有できます。
ぜひご協力ください!

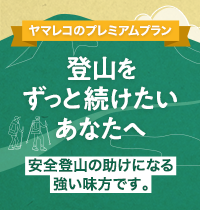








コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する