(はじめに)
「ヨーロッパアルプス」の山々を実際に歩くと、あちこちで変成岩っぽい岩石を見かけます。またスイスのオンライン地質図(文献2)を見ても、あちこちに変成岩類が分布していることがわかります。この点は、火成岩(火山岩、深成岩)や堆積岩が多い、日本の山々と違う点です。
この章では、「ヨーロッパアルプス」に分布している変成岩を、(文献1)を元に、形成時代順に説明します。なお中生代以前の変成岩は、既に第2部、第3部でも、ある程度取り上げましたので、ここでは簡単に説明し、新生代の「アルプス造山運動」に関連するものについて、(文献1−1)を元に、やや詳しく述べます。
なお 言い訳になりますが、変成作用、変成岩については、地質学のなかでもかなり専門的です。(文献1)のなかでも、形成メカニズムについて十分な説明がないところも多く、また私自身、良く解っていない点も多いので、その点は予めご了承ください。
この章では、「ヨーロッパアルプス」に分布している変成岩を、(文献1)を元に、形成時代順に説明します。なお中生代以前の変成岩は、既に第2部、第3部でも、ある程度取り上げましたので、ここでは簡単に説明し、新生代の「アルプス造山運動」に関連するものについて、(文献1−1)を元に、やや詳しく述べます。
なお 言い訳になりますが、変成作用、変成岩については、地質学のなかでもかなり専門的です。(文献1)のなかでも、形成メカニズムについて十分な説明がないところも多く、また私自身、良く解っていない点も多いので、その点は予めご了承ください。
4−4章―(1)節 「ヨーロッパアルプス」における変成作用の分布状況
(文献1−1)には、「ヨーロッパアルプス」における変成作用の分布状況を示す図があります(変成相; “metamorphic facies” による分類)。その図を、図1シリーズとして添付します(全体図の図1−1と、地域ごとに拡大した、図1−2〜図1−4)。これは(文献1−1)のうち、図6-1を引用したものです。なおこの図1では、「外側地塊」(external massifs)は省略されています。
また、(文献4)にも、この図1の元となった変成作用の分布状況を示す図があります。こちらは「変成相」毎に色分けされ解りやすいので、これも、図2シリーズ(図2−1〜図2−3と、地域ごとに分割)として添付します。(この図は、各地塊が解りやすくなっており、各地塊、地域名を書き込みました。ただし、「地質グループ」の区別はされていません)
図1シリーズを見ると、「ヨーロッパアルプス」を構成する5つの「地質グループ」のうち、「サウスアルパイン系」地質グループ(図1では、くすんだオレンジ色)を除き、広範囲に変成作用が及んでいることが解ります。これらの大部分は、新生代の「アルプス造山運動」に伴う変成作用の影響を表しています。
以下、「ヨーロッパアルプス」の変成作用の分布状況を、図1、図2シリーズに基づいて、各「地質グループ」毎に説明します。なお説明は図1のシリーズ(文献1−1)に従い、「変成相」による説明とし、変成岩の種類は説明しませんが、ご了承ください。
なお「変成相」とはなにか?などについては、「補足説明1」、および図3をご参照ください。
(1)「ペニン系」地質グループ(図1では、青紫色);
「中部アルプス」では「ヨーロッパアルプス」の中軸部に、「西部アルプス」では、ややイタリア側に位置する「ペニン系」地質グループにおける変成作用としては、「角閃岩相」(amphibolite facies;最も密な斜め線)、「青色片岩相」(blue schist facies;青色)、「エクロジャイト相」(eclogite facies;濃い紫色)といった高度な変成作用を受けています。
ただし、「ペニン系」の本体部分から離れた、「ヨーロッパアルプス」の周辺部にあたる「ペニン系」のナップ(スイスプレアルプス地域)と「東部アルプス」のうち北縁部だけは、低変成度の「アンキ型」変成帯(anchi zone ;粗い斜め線)となっています。
「ペニン系」における変成作用の時代は、ほぼすべてが「新生代」(Cenozoic)です。
第(5)節で詳しく説明しますが、「ペニン系」地質グループが受けた、上記の高度な変成作用は、新生代の「アルプス造山運動」に先立つ、「ペニン海」(the Penninic Ocean)の沈み込みと関連しています。
(2)「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループ(図1では、黄緑色);
「中部アルプス」では北側、「西部アルプス」では北西側に位置する「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループにおける変成作用としては、大部分が変成度の低い「アンキ型」変成帯(anchi zone ;粗い斜め線)(注1)や「緑色片岩相」(green schist facies;密な斜め線) となっています。全体的な傾向としては、「ペニン系」に近い場所では「緑色片岩相」、遠い場所は「アンキ型」変成帯となっています。
「東部アルプス」のタウエルン地域では、「タウエルン・フェンスター」地域で「ヘルベチカ系」(基盤岩体を含む)が少し顔を出していますが、ここでは「緑色片岩相」に加え、一部では「角閃岩相」もあり、「西部アルプス」「東部アルプス」とは少し挙動が異なります。
なお、この図1では表現されていませんが、このゾーンに点在する「外側地塊」(external massifs)では、各地塊の大部分が、片麻岩類、結晶片岩類などの変成岩からなっています(なんども変成作用を受けている為か、「変成相」としての区分は不明)。
「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」における変成作用の時代は、すべて「新生代」
(Cenozoic)です。
(3) 「オーストロアルパイン系」地質グループ(図1では、黄色);
「オーストロアルパイン系」地質グループは、「東部アルプス」の大部分に分布していますが、この地質グループにおける変成作用はちょっと複雑です。
中軸部では「緑色片岩相」、北側、南側では、低変成度の「アンキ型」変成帯となっていますが、それらの変成年代は、「白亜紀」(Cretaceous)とされています。
また「東部アルプス」東端部や、「タウエルン地域」の一部で、変成度の高い「エクロジャイト相」、「角閃岩相」が分布しています。この「エクロジャイト相」、「角閃岩相」分布域での変成年代も「白亜紀」中葉の約100Maです。
「オーストロアルパイン系」地質グループは、大部分が、「新生代」ではなく「白亜紀」の変成作用を受けている、いう点で、他の地質グループとは挙動が大きく異なります。この、「オーストロアルパイン系」地質グループだけに「白亜紀」に生じた変成作用は、新生代の「アルプス造山運動」とは別の変成作用とされ、「白亜紀造山運動」と呼ばれる造山運動と関連したものとされています(詳しくは後述)。
「中部アルプス」での「オーストロアルパイン系」地質グループは、「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)と呼ばれる、クリッペ状の地質体(図1ではDBと表記)だけですが、この地質体は、「青色片岩相」の変成作用を受けています。これは、その周辺に広がる「ペニン系」の「変成相」と調和的であり、「東部アルプス」の「オーストロアルパイン系」とは変成履歴が異なるようです。また図1では明記されていませんが、この地質体が変成作用を受けた時代は、「新生代」と推定されており、その点でも「東部アルプス」の「オーストロアルパイン系」とは、挙動が異なります。
(4)「サウスアルパイン系」地質グループ(図1では、くすんだオレンジ色);
「ペリ・アドリアティック断層系」(peri-Adriatic Fault system;図1、図2では赤い線)によって、他の地質グループと分離している(decupling)、「サウスアルパイン系」地質グループは、ほとんどが変成作用をうけていません。ただ「中部アルプス」の「ペニン系」に近い場所のみは、弱い変成作用を受けています(「アンキ型」変成帯)。
また、(文献4)にも、この図1の元となった変成作用の分布状況を示す図があります。こちらは「変成相」毎に色分けされ解りやすいので、これも、図2シリーズ(図2−1〜図2−3と、地域ごとに分割)として添付します。(この図は、各地塊が解りやすくなっており、各地塊、地域名を書き込みました。ただし、「地質グループ」の区別はされていません)
図1シリーズを見ると、「ヨーロッパアルプス」を構成する5つの「地質グループ」のうち、「サウスアルパイン系」地質グループ(図1では、くすんだオレンジ色)を除き、広範囲に変成作用が及んでいることが解ります。これらの大部分は、新生代の「アルプス造山運動」に伴う変成作用の影響を表しています。
以下、「ヨーロッパアルプス」の変成作用の分布状況を、図1、図2シリーズに基づいて、各「地質グループ」毎に説明します。なお説明は図1のシリーズ(文献1−1)に従い、「変成相」による説明とし、変成岩の種類は説明しませんが、ご了承ください。
なお「変成相」とはなにか?などについては、「補足説明1」、および図3をご参照ください。
(1)「ペニン系」地質グループ(図1では、青紫色);
「中部アルプス」では「ヨーロッパアルプス」の中軸部に、「西部アルプス」では、ややイタリア側に位置する「ペニン系」地質グループにおける変成作用としては、「角閃岩相」(amphibolite facies;最も密な斜め線)、「青色片岩相」(blue schist facies;青色)、「エクロジャイト相」(eclogite facies;濃い紫色)といった高度な変成作用を受けています。
ただし、「ペニン系」の本体部分から離れた、「ヨーロッパアルプス」の周辺部にあたる「ペニン系」のナップ(スイスプレアルプス地域)と「東部アルプス」のうち北縁部だけは、低変成度の「アンキ型」変成帯(anchi zone ;粗い斜め線)となっています。
「ペニン系」における変成作用の時代は、ほぼすべてが「新生代」(Cenozoic)です。
第(5)節で詳しく説明しますが、「ペニン系」地質グループが受けた、上記の高度な変成作用は、新生代の「アルプス造山運動」に先立つ、「ペニン海」(the Penninic Ocean)の沈み込みと関連しています。
(2)「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループ(図1では、黄緑色);
「中部アルプス」では北側、「西部アルプス」では北西側に位置する「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループにおける変成作用としては、大部分が変成度の低い「アンキ型」変成帯(anchi zone ;粗い斜め線)(注1)や「緑色片岩相」(green schist facies;密な斜め線) となっています。全体的な傾向としては、「ペニン系」に近い場所では「緑色片岩相」、遠い場所は「アンキ型」変成帯となっています。
「東部アルプス」のタウエルン地域では、「タウエルン・フェンスター」地域で「ヘルベチカ系」(基盤岩体を含む)が少し顔を出していますが、ここでは「緑色片岩相」に加え、一部では「角閃岩相」もあり、「西部アルプス」「東部アルプス」とは少し挙動が異なります。
なお、この図1では表現されていませんが、このゾーンに点在する「外側地塊」(external massifs)では、各地塊の大部分が、片麻岩類、結晶片岩類などの変成岩からなっています(なんども変成作用を受けている為か、「変成相」としての区分は不明)。
「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」における変成作用の時代は、すべて「新生代」
(Cenozoic)です。
(3) 「オーストロアルパイン系」地質グループ(図1では、黄色);
「オーストロアルパイン系」地質グループは、「東部アルプス」の大部分に分布していますが、この地質グループにおける変成作用はちょっと複雑です。
中軸部では「緑色片岩相」、北側、南側では、低変成度の「アンキ型」変成帯となっていますが、それらの変成年代は、「白亜紀」(Cretaceous)とされています。
また「東部アルプス」東端部や、「タウエルン地域」の一部で、変成度の高い「エクロジャイト相」、「角閃岩相」が分布しています。この「エクロジャイト相」、「角閃岩相」分布域での変成年代も「白亜紀」中葉の約100Maです。
「オーストロアルパイン系」地質グループは、大部分が、「新生代」ではなく「白亜紀」の変成作用を受けている、いう点で、他の地質グループとは挙動が大きく異なります。この、「オーストロアルパイン系」地質グループだけに「白亜紀」に生じた変成作用は、新生代の「アルプス造山運動」とは別の変成作用とされ、「白亜紀造山運動」と呼ばれる造山運動と関連したものとされています(詳しくは後述)。
「中部アルプス」での「オーストロアルパイン系」地質グループは、「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)と呼ばれる、クリッペ状の地質体(図1ではDBと表記)だけですが、この地質体は、「青色片岩相」の変成作用を受けています。これは、その周辺に広がる「ペニン系」の「変成相」と調和的であり、「東部アルプス」の「オーストロアルパイン系」とは変成履歴が異なるようです。また図1では明記されていませんが、この地質体が変成作用を受けた時代は、「新生代」と推定されており、その点でも「東部アルプス」の「オーストロアルパイン系」とは、挙動が異なります。
(4)「サウスアルパイン系」地質グループ(図1では、くすんだオレンジ色);
「ペリ・アドリアティック断層系」(peri-Adriatic Fault system;図1、図2では赤い線)によって、他の地質グループと分離している(decupling)、「サウスアルパイン系」地質グループは、ほとんどが変成作用をうけていません。ただ「中部アルプス」の「ペニン系」に近い場所のみは、弱い変成作用を受けています(「アンキ型」変成帯)。
4−4章―(2)節 原生代〜古生代前半の変成岩(アルトクリスタリン)
この第(2)節から第(4)節までは、時代別に、「アルプス地域」(Alpine Domain)が受けた変成作用、変成岩について説明していきます。但し、以前の章でも説明しているところは、簡単に説明します。
「ヨーロッパアルプス」に分布する変成岩のうち、最も古いものは、「アルトクリスタリン」(Altkristallin(独))と呼ばれる、複数回の変成作用を受けた変成岩類です(文献7)。原岩は主に、原生代に起源を持つ、堆積岩や玄武岩質の火成岩と推定されており、原生代から古生代前半までに複数回の変成作用を受け、さらに、古生代後半期の「ヴァリスカン造山運動」、新生代の「アルプス造山運動」による影響も受けているものと推定されています。
この「アルトクリスタリン」は、「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループ分布域にある、「外側地塊」(external massifs)の中に含まれており、元々は地下深くに伏在していたものが、「アルプス造山運動」によって「外側地塊」群が、上部地殻から分離しつつ隆起したため、地表に現れているものです。その他、「東部アルプス」の「タウエルン地域」内にある「基盤岩体」も、「外側地塊」と同類です。
「アルトクリスタリン」が分布する主要な「外側地塊」としては、スイスのベルナーオーバーラント山群に相当する「アール地塊」(Aar massif)や、フランスの「エギーユ・ルージュ地塊」(Aiguilles Rouges massif)があります。またオーストリアの「タウエルン地域」(Tauern zone)の中心部の基盤岩体も同類です。
「アルトクリスタリン」と称される変成岩類は、具体的な岩石としては「片麻岩」類(gneisses)が多く、その他には、「結晶片岩」類(schists)、「ミグマタイト」(migmatite)も含んでいます。
「アルトクリスタリン」については、この連載の2−1章にて、詳しく説明していますので、そちらもご覧ください。
「ヨーロッパアルプス」に分布する変成岩のうち、最も古いものは、「アルトクリスタリン」(Altkristallin(独))と呼ばれる、複数回の変成作用を受けた変成岩類です(文献7)。原岩は主に、原生代に起源を持つ、堆積岩や玄武岩質の火成岩と推定されており、原生代から古生代前半までに複数回の変成作用を受け、さらに、古生代後半期の「ヴァリスカン造山運動」、新生代の「アルプス造山運動」による影響も受けているものと推定されています。
この「アルトクリスタリン」は、「ヘルベチカ系」、「ドーフィネ系」地質グループ分布域にある、「外側地塊」(external massifs)の中に含まれており、元々は地下深くに伏在していたものが、「アルプス造山運動」によって「外側地塊」群が、上部地殻から分離しつつ隆起したため、地表に現れているものです。その他、「東部アルプス」の「タウエルン地域」内にある「基盤岩体」も、「外側地塊」と同類です。
「アルトクリスタリン」が分布する主要な「外側地塊」としては、スイスのベルナーオーバーラント山群に相当する「アール地塊」(Aar massif)や、フランスの「エギーユ・ルージュ地塊」(Aiguilles Rouges massif)があります。またオーストリアの「タウエルン地域」(Tauern zone)の中心部の基盤岩体も同類です。
「アルトクリスタリン」と称される変成岩類は、具体的な岩石としては「片麻岩」類(gneisses)が多く、その他には、「結晶片岩」類(schists)、「ミグマタイト」(migmatite)も含んでいます。
「アルトクリスタリン」については、この連載の2−1章にて、詳しく説明していますので、そちらもご覧ください。
4−4章―(3)節 「ヴァリスカン造山運動」に伴う変成岩
古生代の後半期(「デボン紀」〜「ペルム紀」)、「ヨーロッパ」大陸ブロックでは、「ヴァリスカン造山運動」(the Variscan orogeny)(文献8)と呼ばれる造山運動が起こり、「ヨーロッパアルプス」の中にも、その「ヴァリスカン造山運動」に関連した変成岩が点在しています。ただし、あまりまとまった岩体としては残っていないようです。
これについては、この連載の2−2章にて、まとめて説明をしていますので、ここでは詳しい説明は省きます。詳しくは2−2章をご覧ください。
これについては、この連載の2−2章にて、まとめて説明をしていますので、ここでは詳しい説明は省きます。詳しくは2−2章をご覧ください。
4−4章―(4)節 「東部アルプス」における白亜紀の変成岩と「白亜紀造山運動」
(文献1−1)や、添付の図1―1,図1−4によると、「東部アルプス」に広がる「オーストロアルパイン系」地質グループは、その大部分が「白亜紀」中葉(約110〜90Ma)に変成作用を受けている、とされており、変成年代が新生代である「中部アルプス」、「西部アルプス」とは異なっています。
「東部アルプス」の「変成相」分布の様子は、図1−4と図2−3に示していますが、より解りやすい図2―3で説明します。各「変成相」については、図3もご参照ください。
まず「東部アルプス」の東部(Graz市付近)と、「タウエルン地域」の南側には、「エクロジャイト相」分布域(図2―3では紫色)があります。
それ以外の「東部アルプス」中軸部は、「角閃岩相」(赤色)、「緑色片岩相」(黄緑色系統)、およびその中間的な相(ベージュ色)となっています。
「タウエルン地域」のフェンスター内は、主に「ペニン系」と「基盤岩体」(crystalline basement)分布域で、「オーストロアルパイン系」地質グループではありませんが、「角閃岩相」(赤色)、「青色片岩相」(水色)などとなっています。図1−4によると、フェンスター内の変成時代は新生代であり、「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域とは異なる変成作用です。
「東部アルプス」の北部、「北カルカレウス山脈」付近は、低変成度の「アンキ型」変成帯(anchi zone)(黄色、薄いベージュ色)で、具体的には「沸石相」、「ぶどう石・パンペリー石相」などとなっています。
「東部アルプス」の南部、「ペリ・アドリアティック断層系」付近の「南石灰岩アルプス」(カルニックアルプス)でも、低変成度の「アンキ型」変成帯となっています。
なお、「ペリ・アドリアティック断層系」(図2―3では赤い線)より南側は、「サウスアルパイン系」地質グループ分布域(ドロミティ地域など)ですが、ここは非変成であり、「オーストロアルパイン系」ゾーンとは、変成作用の点でまったく異なる履歴です。
全体的に見ると、「東部アルプス」の中軸部で高変成度の「変成相」ゾーンが分布し、北側、南側では低変成度な「変成相」ゾーン、という傾向が認められます。
この、「東部アルプス」の「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域に痕跡を残している、「白亜紀」中葉の変成作用に関しては、「白亜紀造山運動」(the Cretaceous orogeny)に関連しているとして、(文献1−2)、(文献1−4)に説明があります。
それによると、新生代の「アルプス造山運動」が始まる前、「白亜紀」中葉から後期(約110〜65Ma)にかけて、「アドリア大陸ブロック」のマージン部の一部であった、「オーストロアルパイン地質区」では、「白亜紀造山運動」と呼ばれる造山運動が起こった、と推定されています。
これは、「白亜紀」中葉(?)から始まった、「ペニン海」(the Penninic Ocean)(注2)の「アドリア大陸ブロック」の下への沈み込みに伴うものです(文献1−4)。
その沈み込みによって地下深くに沈み込んだ「ペニン系」の地質体は、高圧型の変成作用を受け、「エクロジャイト相」、「青色片岩相」などの高圧型変成岩となった、と推定されています。
ただし、当時の「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域は、沈み込み帯の上盤側
(hanging wall)にあって、地下深部に沈み込んだわけではなく、逆に隆起して山地を形成したことになるので、なぜ「オーストロアルパイン系」地質グループまでもが、広範囲に変成作用を受けたのかは、疑問が残ります。(文献1−1)、(文献1−2)でも、その点の説明はあやふやです。
一つの考え方としては、沈み込んで高圧型変成作用を受けた「ペニン系」地質グループの一部が、フラグメント化しつつ上昇し、「オーストロアルパイン系」地質グループに混入している、とも考えられます(この段落は私見です)。
なお、(文献1−2)によると、この「白亜紀造山運動」の痕跡は、「東部アルプス」北側の「北カルカレウス山脈」に色々な証拠がある(白亜紀中葉から後期に活動したスラスト断層群、隆起した山地から供給された破砕性堆積物の存在など)、とも説明されており、造山運動が起こったこと自体は確実のようです。
「東部アルプス」の「オーストロアルパイン系」地質グループにおける、具体的な岩石の種類ですが、(文献1―4)の「東部アルプス」の地質図(図5-3-1)によると、「グレーワッケ」(Greywacke)と呼ばれる、古生代の砂質堆積岩、「クオーツ・フィライト」(Quartz Phyllite)と呼ばれる、古生代の泥質堆積岩が変成作用を受けた、千枚岩(フィライト;phyllite)、中生代(主に「トリアス紀」)の石灰岩類(北カルカレウス山脈、南部石灰岩アルプス)、およびそれらの構造的下位にあたる、基盤岩体(crystalline basements)(具体的には、古生代、それ以前に変成作用をうけてできた片麻岩類、結晶片岩類)です。
(文献1−4)の説明ではざっくりしすぎているので、「東部アルプス」における実際の変成岩の分布を、オーストリアのオンライン地質図(文献3)(5万分1 地質図レイヤー)で確認してみました。
説明文がドイツ語である点や、変成時代や「変成相」が書かれていないこともあり、詳しくは解りませんが、「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域では、以下のような高度変成岩が認められます。ただし、これらが、古生代に変成作用を受けた「基盤岩体」に属するのか、「白亜紀」の変成岩なのかは、はっきりしません。
・「東部アルプス」東部、Graz市付近に、「エクロジャイト」(Eklogit(独))、「エクロジャイト/角閃岩」(Eklogit amphibolit(独))、「エクロジャイト/変成ハンレイ岩」(Eklogit-Gabbro(独)))、が、小岩体として点在しています。
・「東部アルプス」中部、「タウエルン・フェンスター」の南側では、「角閃岩」
(Amphibolit(独))が点在しています。
・「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域全般で、「基盤岩体」に属すると思われますが、「片麻岩類」(Ortho-Gneis, Para-Gneis(独))や「雲母片岩」(Glimmer-Schiefer(独))などが、広範囲に分布しています。
「東部アルプス」の「変成相」分布の様子は、図1−4と図2−3に示していますが、より解りやすい図2―3で説明します。各「変成相」については、図3もご参照ください。
まず「東部アルプス」の東部(Graz市付近)と、「タウエルン地域」の南側には、「エクロジャイト相」分布域(図2―3では紫色)があります。
それ以外の「東部アルプス」中軸部は、「角閃岩相」(赤色)、「緑色片岩相」(黄緑色系統)、およびその中間的な相(ベージュ色)となっています。
「タウエルン地域」のフェンスター内は、主に「ペニン系」と「基盤岩体」(crystalline basement)分布域で、「オーストロアルパイン系」地質グループではありませんが、「角閃岩相」(赤色)、「青色片岩相」(水色)などとなっています。図1−4によると、フェンスター内の変成時代は新生代であり、「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域とは異なる変成作用です。
「東部アルプス」の北部、「北カルカレウス山脈」付近は、低変成度の「アンキ型」変成帯(anchi zone)(黄色、薄いベージュ色)で、具体的には「沸石相」、「ぶどう石・パンペリー石相」などとなっています。
「東部アルプス」の南部、「ペリ・アドリアティック断層系」付近の「南石灰岩アルプス」(カルニックアルプス)でも、低変成度の「アンキ型」変成帯となっています。
なお、「ペリ・アドリアティック断層系」(図2―3では赤い線)より南側は、「サウスアルパイン系」地質グループ分布域(ドロミティ地域など)ですが、ここは非変成であり、「オーストロアルパイン系」ゾーンとは、変成作用の点でまったく異なる履歴です。
全体的に見ると、「東部アルプス」の中軸部で高変成度の「変成相」ゾーンが分布し、北側、南側では低変成度な「変成相」ゾーン、という傾向が認められます。
この、「東部アルプス」の「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域に痕跡を残している、「白亜紀」中葉の変成作用に関しては、「白亜紀造山運動」(the Cretaceous orogeny)に関連しているとして、(文献1−2)、(文献1−4)に説明があります。
それによると、新生代の「アルプス造山運動」が始まる前、「白亜紀」中葉から後期(約110〜65Ma)にかけて、「アドリア大陸ブロック」のマージン部の一部であった、「オーストロアルパイン地質区」では、「白亜紀造山運動」と呼ばれる造山運動が起こった、と推定されています。
これは、「白亜紀」中葉(?)から始まった、「ペニン海」(the Penninic Ocean)(注2)の「アドリア大陸ブロック」の下への沈み込みに伴うものです(文献1−4)。
その沈み込みによって地下深くに沈み込んだ「ペニン系」の地質体は、高圧型の変成作用を受け、「エクロジャイト相」、「青色片岩相」などの高圧型変成岩となった、と推定されています。
ただし、当時の「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域は、沈み込み帯の上盤側
(hanging wall)にあって、地下深部に沈み込んだわけではなく、逆に隆起して山地を形成したことになるので、なぜ「オーストロアルパイン系」地質グループまでもが、広範囲に変成作用を受けたのかは、疑問が残ります。(文献1−1)、(文献1−2)でも、その点の説明はあやふやです。
一つの考え方としては、沈み込んで高圧型変成作用を受けた「ペニン系」地質グループの一部が、フラグメント化しつつ上昇し、「オーストロアルパイン系」地質グループに混入している、とも考えられます(この段落は私見です)。
なお、(文献1−2)によると、この「白亜紀造山運動」の痕跡は、「東部アルプス」北側の「北カルカレウス山脈」に色々な証拠がある(白亜紀中葉から後期に活動したスラスト断層群、隆起した山地から供給された破砕性堆積物の存在など)、とも説明されており、造山運動が起こったこと自体は確実のようです。
「東部アルプス」の「オーストロアルパイン系」地質グループにおける、具体的な岩石の種類ですが、(文献1―4)の「東部アルプス」の地質図(図5-3-1)によると、「グレーワッケ」(Greywacke)と呼ばれる、古生代の砂質堆積岩、「クオーツ・フィライト」(Quartz Phyllite)と呼ばれる、古生代の泥質堆積岩が変成作用を受けた、千枚岩(フィライト;phyllite)、中生代(主に「トリアス紀」)の石灰岩類(北カルカレウス山脈、南部石灰岩アルプス)、およびそれらの構造的下位にあたる、基盤岩体(crystalline basements)(具体的には、古生代、それ以前に変成作用をうけてできた片麻岩類、結晶片岩類)です。
(文献1−4)の説明ではざっくりしすぎているので、「東部アルプス」における実際の変成岩の分布を、オーストリアのオンライン地質図(文献3)(5万分1 地質図レイヤー)で確認してみました。
説明文がドイツ語である点や、変成時代や「変成相」が書かれていないこともあり、詳しくは解りませんが、「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域では、以下のような高度変成岩が認められます。ただし、これらが、古生代に変成作用を受けた「基盤岩体」に属するのか、「白亜紀」の変成岩なのかは、はっきりしません。
・「東部アルプス」東部、Graz市付近に、「エクロジャイト」(Eklogit(独))、「エクロジャイト/角閃岩」(Eklogit amphibolit(独))、「エクロジャイト/変成ハンレイ岩」(Eklogit-Gabbro(独)))、が、小岩体として点在しています。
・「東部アルプス」中部、「タウエルン・フェンスター」の南側では、「角閃岩」
(Amphibolit(独))が点在しています。
・「オーストロアルパイン系」地質グループ分布域全般で、「基盤岩体」に属すると思われますが、「片麻岩類」(Ortho-Gneis, Para-Gneis(独))や「雲母片岩」(Glimmer-Schiefer(独))などが、広範囲に分布しています。
4−4章―(5)節 新生代の「アルプス造山運動」に伴う「高圧型変成作用」
(文献1―1)では、新生代の「アルプス造山運動」に伴って生じた変成作用を、以下2種類にわけています。
・タイプA) (低温)高圧型変成作用で、主な変成相は「エクロジャイト相」、
「青色片岩相」。
主に「中部アルプス」の「ペニン系」地質ゾーンに存在するが、
「西部アルプス」の「ペニン系」にも存在する。
変成ピーク時期は、古第三紀「始新世」。
・タイプB) (低圧)高温型の変成作用で、主な変成相は「角閃岩相」、「緑色片岩相」。
「中部アルプス」のうち「レポンティン地域」(注5)(主に「ペニン系」)に
分布する。
タイプA)の変成作用が起きた後に生じた、やや局所的な変成作用。
変成ピーク時期は、古第三紀「漸新世」から新第三紀「中新世」初頭。
この第(5)節では、上記のうちタイプA)の高圧型変成作用について説明します。タイプB)の高温型変成作用については、次の第(6)節で説明します。
(文献1−1)によると、タイプA)の変成作用は、「中部アルプス」の「ペニン系」の各地質体に、広範に認められています(後述のように、スイスのオンライン地質図(文献2)では、明らかではないのですが)。
(文献1−1)の図6−2、図6−4に、「P-T-t」図と共に説明されている地質体は、「中部アルプス」の「ペニン系」地質体として、「ツエルマット・ザースフェー」地質体(Zermatt Saas-Fee zone)、「タンボ」(Tambo)地質体、「アドーラ」(Adura)地質体、「アルプ・アラーミ」(Alpe Arami)岩体、及び「オーストロアルパイン系」地質グループに属するクリッペである「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)、「西部アルプス」の「ペニン系」地質体である「ドーラ・マイーラ」(Dora Maira)地質体、「東部アルプス」では、「エッツタール」(Oetztal )地質体(「オーストロアルパイン系」)、「タウエルン地域」(Tauern)のうち、フェンスター内の「エクロジャイトゾーン」があります。
これらすべてを説明すると冗長になりすぎるので、代表として「ツエルマット・ザースフェー」地質体について説明します。添付の図4もご参照ください。これは(文献1−1)の、図6-2からの引用です。
この地質体は元々、「ペニン海」(the Penninic Ocean)地質区のうち、「ピエモンテ海」(the Piemont Ocean)の海洋プレートを形成していたもので、「白亜紀」中葉から始まる、「ペニン海」の「アドリア大陸ブロック」の下への沈み込みによって地下深くに運ばれ、約44Ma(古第三紀「始新世」)には、約3GPaの圧力下に達しました(温度は約550℃、変成相としては「エクロジャイト相」に相当)。
静水圧条件(lithostatic)を仮定し、かつ地殻、上部マントルの平均密度を約3g/cm^3 とすると、深さ(D)=約100kmに相当します(ただし動的圧力(tectonic overpressure)(注3)を考慮すると、もっと浅く、D=50〜70kmあたりかもしれない)。
その後、急速に反転上昇に移り、ほぼ断熱的に上昇し(=温度はあまり変化なく、圧力だけが急速に低下)、約38Maには、約0.5GPa(温度は約500℃)の条件下に至りました(静水圧条件で試算すると、D=約15km)。その後はゆっくりと温度が低下しつつ、現在に至る、という遍歴です。
「中部アルプス」や「西部アルプス」の、その他の「ペニン系」地質体、例えば「タンボ」(Tambo)地質体、「アドーラ」(Adura)地質体、「ドーラ・マイーラ」(Dora Maira)地質体(西部アルプス)も、(文献1−1)に記載の「P−T−t」図によると、大まかな挙動は類似しており、45〜30Ma(古第三紀「始新世」〜「漸新世」)に、最大圧力下(最大深度)となり、その後、急速に地上へ向かって上昇する(断熱的上昇)、というパターンとなっています。
その結果として、現世の「西部アルプス」、「中部アルプス」の「ペニン系」ゾーンには、「エクロジャイト相」、「青色片岩相」の高圧型変成岩が分布している、と(文献1−1)では説明されています。
なお「中部アルプス」の「ペニン系」ゾーンにおける、具体的な変成岩の種類を、スイスのオンライン地質図(文献2)で実際に確認してみると、片麻岩類(Gneis(独))、結晶片岩類(Schifer(独))、角閃岩(Amphibolit(独))、蛇紋岩(Serpentinit(独));マントルカンラン岩由来の変成岩)、変成斑レイ岩(meta-gabllo)といった変成岩が分布しています。ただし「変成相」の記載はないので、(文献1−1)の記載のような「エクロジャイト相」、「青色片岩相」の変成岩かどうかは、はっきりしません
いずれにしろ、(文献1)の説明によると、現世の「ペニン系」ゾーンにおける高圧型変成岩の存在が逆に、「ペニン系」地質グループが沈み込み帯で地下深部へと沈み込んで、その結果として「ペニン海」が無くなってしまい、最終的には「ヨーロッパ大陸ブロック」と「アドリア大陸ブロック」とが衝突した、という「アルプス造山運動」のシナリオの根拠のひとつとなっています。
また3−3章で説明した、見てきたかのような、「アルプス造山運動」の各時代における推定地質断面図も、このような変成岩の解析が根拠となっています。
ところで、(文献1)ではほとんど説明がありませんが、これら「アルプス造山運動」の最中に形成された高圧型変成岩のうち、特記すべきものは、「ヨーロッパアルプス」の中に、約2〜3GPa以上でしか安定でない、超高圧型変成鉱物である「コ―サイト」(coesite)(注3)が発見されたことが挙げられます(文献9)、(文献10)、(文献11)。
(文献9)などによると、「コ―サイト」は、「西部アルプス」の「ドーラ・マイーラ」(Dora Maira)地質体にて、最初に確認されています。
この「コーサイト」の存在は、現在では逆に、衝突型の造山運動が起きた証拠とみなされており、「ヒマラヤ山脈」や中国(国)東部の「大別山・山脈」(the Dabie-Shan Range)でも確認されています。それが、「ヒマラヤ山脈」が「インド地塊」のユーラシアプレートへの衝突により形成されたこと、中国(国)の主要部が、「北中国地塊」と「南中国地塊」との衝突により合体したことの証拠の一つとなっています。
・タイプA) (低温)高圧型変成作用で、主な変成相は「エクロジャイト相」、
「青色片岩相」。
主に「中部アルプス」の「ペニン系」地質ゾーンに存在するが、
「西部アルプス」の「ペニン系」にも存在する。
変成ピーク時期は、古第三紀「始新世」。
・タイプB) (低圧)高温型の変成作用で、主な変成相は「角閃岩相」、「緑色片岩相」。
「中部アルプス」のうち「レポンティン地域」(注5)(主に「ペニン系」)に
分布する。
タイプA)の変成作用が起きた後に生じた、やや局所的な変成作用。
変成ピーク時期は、古第三紀「漸新世」から新第三紀「中新世」初頭。
この第(5)節では、上記のうちタイプA)の高圧型変成作用について説明します。タイプB)の高温型変成作用については、次の第(6)節で説明します。
(文献1−1)によると、タイプA)の変成作用は、「中部アルプス」の「ペニン系」の各地質体に、広範に認められています(後述のように、スイスのオンライン地質図(文献2)では、明らかではないのですが)。
(文献1−1)の図6−2、図6−4に、「P-T-t」図と共に説明されている地質体は、「中部アルプス」の「ペニン系」地質体として、「ツエルマット・ザースフェー」地質体(Zermatt Saas-Fee zone)、「タンボ」(Tambo)地質体、「アドーラ」(Adura)地質体、「アルプ・アラーミ」(Alpe Arami)岩体、及び「オーストロアルパイン系」地質グループに属するクリッペである「ダンブランシュ・ナップ」(Dent Blanche nappe)、「西部アルプス」の「ペニン系」地質体である「ドーラ・マイーラ」(Dora Maira)地質体、「東部アルプス」では、「エッツタール」(Oetztal )地質体(「オーストロアルパイン系」)、「タウエルン地域」(Tauern)のうち、フェンスター内の「エクロジャイトゾーン」があります。
これらすべてを説明すると冗長になりすぎるので、代表として「ツエルマット・ザースフェー」地質体について説明します。添付の図4もご参照ください。これは(文献1−1)の、図6-2からの引用です。
この地質体は元々、「ペニン海」(the Penninic Ocean)地質区のうち、「ピエモンテ海」(the Piemont Ocean)の海洋プレートを形成していたもので、「白亜紀」中葉から始まる、「ペニン海」の「アドリア大陸ブロック」の下への沈み込みによって地下深くに運ばれ、約44Ma(古第三紀「始新世」)には、約3GPaの圧力下に達しました(温度は約550℃、変成相としては「エクロジャイト相」に相当)。
静水圧条件(lithostatic)を仮定し、かつ地殻、上部マントルの平均密度を約3g/cm^3 とすると、深さ(D)=約100kmに相当します(ただし動的圧力(tectonic overpressure)(注3)を考慮すると、もっと浅く、D=50〜70kmあたりかもしれない)。
その後、急速に反転上昇に移り、ほぼ断熱的に上昇し(=温度はあまり変化なく、圧力だけが急速に低下)、約38Maには、約0.5GPa(温度は約500℃)の条件下に至りました(静水圧条件で試算すると、D=約15km)。その後はゆっくりと温度が低下しつつ、現在に至る、という遍歴です。
「中部アルプス」や「西部アルプス」の、その他の「ペニン系」地質体、例えば「タンボ」(Tambo)地質体、「アドーラ」(Adura)地質体、「ドーラ・マイーラ」(Dora Maira)地質体(西部アルプス)も、(文献1−1)に記載の「P−T−t」図によると、大まかな挙動は類似しており、45〜30Ma(古第三紀「始新世」〜「漸新世」)に、最大圧力下(最大深度)となり、その後、急速に地上へ向かって上昇する(断熱的上昇)、というパターンとなっています。
その結果として、現世の「西部アルプス」、「中部アルプス」の「ペニン系」ゾーンには、「エクロジャイト相」、「青色片岩相」の高圧型変成岩が分布している、と(文献1−1)では説明されています。
なお「中部アルプス」の「ペニン系」ゾーンにおける、具体的な変成岩の種類を、スイスのオンライン地質図(文献2)で実際に確認してみると、片麻岩類(Gneis(独))、結晶片岩類(Schifer(独))、角閃岩(Amphibolit(独))、蛇紋岩(Serpentinit(独));マントルカンラン岩由来の変成岩)、変成斑レイ岩(meta-gabllo)といった変成岩が分布しています。ただし「変成相」の記載はないので、(文献1−1)の記載のような「エクロジャイト相」、「青色片岩相」の変成岩かどうかは、はっきりしません
いずれにしろ、(文献1)の説明によると、現世の「ペニン系」ゾーンにおける高圧型変成岩の存在が逆に、「ペニン系」地質グループが沈み込み帯で地下深部へと沈み込んで、その結果として「ペニン海」が無くなってしまい、最終的には「ヨーロッパ大陸ブロック」と「アドリア大陸ブロック」とが衝突した、という「アルプス造山運動」のシナリオの根拠のひとつとなっています。
また3−3章で説明した、見てきたかのような、「アルプス造山運動」の各時代における推定地質断面図も、このような変成岩の解析が根拠となっています。
ところで、(文献1)ではほとんど説明がありませんが、これら「アルプス造山運動」の最中に形成された高圧型変成岩のうち、特記すべきものは、「ヨーロッパアルプス」の中に、約2〜3GPa以上でしか安定でない、超高圧型変成鉱物である「コ―サイト」(coesite)(注3)が発見されたことが挙げられます(文献9)、(文献10)、(文献11)。
(文献9)などによると、「コ―サイト」は、「西部アルプス」の「ドーラ・マイーラ」(Dora Maira)地質体にて、最初に確認されています。
この「コーサイト」の存在は、現在では逆に、衝突型の造山運動が起きた証拠とみなされており、「ヒマラヤ山脈」や中国(国)東部の「大別山・山脈」(the Dabie-Shan Range)でも確認されています。それが、「ヒマラヤ山脈」が「インド地塊」のユーラシアプレートへの衝突により形成されたこと、中国(国)の主要部が、「北中国地塊」と「南中国地塊」との衝突により合体したことの証拠の一つとなっています。
4−4章―(6)節 「アルプス造山運動」における「高温型変成作用」
前の第(5)節でも述べたように、(文献1−1)によると、新生代の「アルプス造山運動」における変成作用としては、最初に「高圧型」の変成作用が、「中部アルプス」、「西部アルプス」の「ペニン系」地質グループにおいて生じ、その後、「高温型」の、やや局所的な変成作用が、「中部アルプス」の「ペニン系」、「ヘルベチカ系」地質グループなどに対して生じた、というシナリオが説明されています。
この第(6)節では、「高温型変成作用」について、(文献1−1)を元に説明します。
(文献1−1)によると「中部アルプス」の「レポンティン地域」(the Lepontine area)注5)と呼ばれる、主に「ペニン系」地質グループが分布する地域では、約28〜21Ma(古第三紀「漸新世」〜新第三紀「中新世」初頭)において、最高温度(Tmax)=650℃程度、最高圧力(Pmax)=0.7GPa程度の条件化での変成作用が生じた、とされています。この温度、圧力条件は「変成相図」(図4)でみると、「角閃岩相」(Amphibolite facies)に相当し、図5でも「角閃岩相」として表示されています。
温度(T)、圧力(P)は、「レポンティン地域」の中心部(「ペニン系」分布域)で大きく、周辺部に向かっては低下し、周辺部(「ヘルベチカ系」分布域、「アール地塊」、「ゴッタルト地塊」)では「緑色片岩相」(green-schist facies)に相当する条件になっています。
この高温型変成作用が生じた際の、推定温度分布を、図5として示します。これは(文献1−1)の、図6-5-(c)を引用したものです。
この、ある程度局所的な「高温型変成作用」が生じたテクトニクスについて、(文献1−1)では十分な説明がなく、良く解りません。
現在の地質構造と調和的な変成度分布を示すことから、この時代(約28〜21Ma)は、既に現世とおなじような地質構造が形成されており、その後に、この変成作用が生じた、と考えられています。
また「ナップパイル構造」形成との関連があるようにも書かれていますが、詳しいことは不明です。
なお、この節の内容の元文献は(文献14)で、こちらのほうが、多少は詳しく書かれています。
この第(6)節では、「高温型変成作用」について、(文献1−1)を元に説明します。
(文献1−1)によると「中部アルプス」の「レポンティン地域」(the Lepontine area)注5)と呼ばれる、主に「ペニン系」地質グループが分布する地域では、約28〜21Ma(古第三紀「漸新世」〜新第三紀「中新世」初頭)において、最高温度(Tmax)=650℃程度、最高圧力(Pmax)=0.7GPa程度の条件化での変成作用が生じた、とされています。この温度、圧力条件は「変成相図」(図4)でみると、「角閃岩相」(Amphibolite facies)に相当し、図5でも「角閃岩相」として表示されています。
温度(T)、圧力(P)は、「レポンティン地域」の中心部(「ペニン系」分布域)で大きく、周辺部に向かっては低下し、周辺部(「ヘルベチカ系」分布域、「アール地塊」、「ゴッタルト地塊」)では「緑色片岩相」(green-schist facies)に相当する条件になっています。
この高温型変成作用が生じた際の、推定温度分布を、図5として示します。これは(文献1−1)の、図6-5-(c)を引用したものです。
この、ある程度局所的な「高温型変成作用」が生じたテクトニクスについて、(文献1−1)では十分な説明がなく、良く解りません。
現在の地質構造と調和的な変成度分布を示すことから、この時代(約28〜21Ma)は、既に現世とおなじような地質構造が形成されており、その後に、この変成作用が生じた、と考えられています。
また「ナップパイル構造」形成との関連があるようにも書かれていますが、詳しいことは不明です。
なお、この節の内容の元文献は(文献14)で、こちらのほうが、多少は詳しく書かれています。
4−4章ー(7)項 「ヨーロッパアルプス」における、具体的な変成岩(例)
ここまで、文章と図だけで、「ヨーロッパアルプス」における、変成作用、変成岩について説明してきました。
文章ばかりでは解りにくいと思いますので、「ヨーロッパアルプス」における具体的な変成岩をいくつか、写真として添付しましたのでご参照ください。
図7は、高圧型変成岩の代表である「エクロジャイト」で、(文献16)から引用しました。
※ (文献16)によると、この写真の著作権は、「オックスフォード大学」にありますが、「教育用なら無料で使用可」との注釈があり、「教育用」ということとして、引用してます。
図8,9は、筆者撮影がスイスの「グリンデルワルド」近郊で観察した、「片麻岩類」、「千枚岩」と思われる変成岩です。
なお(文献16)は、オックスフォード大学(英)の地質学に関する教育用のサイトですが、変成岩の写真が多く、勉強になりました。
文章ばかりでは解りにくいと思いますので、「ヨーロッパアルプス」における具体的な変成岩をいくつか、写真として添付しましたのでご参照ください。
図7は、高圧型変成岩の代表である「エクロジャイト」で、(文献16)から引用しました。
※ (文献16)によると、この写真の著作権は、「オックスフォード大学」にありますが、「教育用なら無料で使用可」との注釈があり、「教育用」ということとして、引用してます。
図8,9は、筆者撮影がスイスの「グリンデルワルド」近郊で観察した、「片麻岩類」、「千枚岩」と思われる変成岩です。
なお(文献16)は、オックスフォード大学(英)の地質学に関する教育用のサイトですが、変成岩の写真が多く、勉強になりました。
オックスフォード大学(英)の地質学に関する教育用サイトのうち、各種変成岩の写真
【他の連載へのリンク】
この連載の各項目へのリンクがあります
一つ前の連載へのリンクです
次の連載へのリンクです
【注釈の項】
注1) 「アンキ型」変成帯(anchi zone)について
変成岩に関する教科書類(文献5)、(文献6)には、「アンキ型」というものは記載されておらず、はっきりとは分かりません。一方、地学事典(文献17)では、「アンキ変成帯」(anchi zone)、「アンキ変成作用」(anchimet morphism)という用語の説明があり、それらの項から考えると、「変成相」でいうと「沸石相」(zeolite facies)、「ぶどう石・パンペリー石相」(prehnite-pumpellyite facies)など、低変成度(かなり低温、低圧条件下)の変成岩に相当するようです。(「イライト」という変成鉱物の結晶化度によって決める変成岩の分類方法であり、「変成相」や「変成分帯」で分類する一般的な方法とは異なる)。
注2) 「ペニン海」(the Penninic Ocean)について
中生代の「ジュラ紀」、「白亜紀」にかけて、「ヨーロッパ大陸ブロック」と「アドリア大陸ブロック」との間に、大西洋側からリフトゾーンを伴った細長い海域が形成されました(この連載の、第2―4章、第2−5章もご参照ください)。
この海域は、「ピエモンテ・リグーニア海」(Piemont-Liguria Ocean)や、「アルパイン・テティス海」(Alpine Tethys)など、文献によって様々に呼ばれ、一定していませんが、この連載では、「ペニン海」という名称で統一しています。
「ペニン海」はさらに、南側から順に、比較的幅の広い海洋である「ピエモンテ海」(the Piemont Ocean)、細長い半島状のゾーンである「ブリアンソン・ライズ」(Briançon rise)、幅の狭いリフトゾーンである「ヴァリストラフ」(Valais trough)、の3つの亜区に分けられます。この連載の第2部(古生代〜中生代のアルプス地域の地史)にも説明していますので、そちらもご参照ください。
注3) 「沈み込み帯」における「静的な圧力」と「動的な圧力」について
この件は「補足説明3」に、解る範囲でまとめてみました。
注4) 「コーサイト」について
「コーサイト」(coesite)という鉱物は、日本語では「コース石」とも呼びますが、化学組成は「SiO2」であり、石英(quartz)の高圧相にあたる鉱物です。両者には、結晶構造の違いがあるだけで、化学組成は同じです。
(文献9)によると、約2〜3GPa以上の圧力下では「石英」相より「コーサイト」相が安定となります(正確には温度(T)にも依存するので、その境界線(相転移ライン)は「P-T」図上で示され、低温側では約2GPa、高温側では、約3Ga)。
圧力(P)=2.5GPaとして深さを見積もると、静水圧条件(lithostatic)で、かつ地殻、上部マントルの密度を、約3g/cm^3と仮定すると、約75kmの深さに相当します。
注5) 「レポンティン地域」について
(文献1)では、「レポンティン地域」(the Lepontine area)や「レポンティン・ドーム」(Lepontine Dome)という言葉がしばしば出てきますが、(文献1)の地質図には場所が明記されていません。
(文献15)(ウイキペディア英語版の、レポンティン・アルプス)の項によると、「中部アルプス」のうち、スイス南部の、ティチーノ州(Ticino)を中心とし、その東側にあたるグラウビュンデン州(Graubünden)の西部や、その西側にあたるヴァリス州(Valais)の東部にかけて、及び国境を越えたイタリア北部のロンバルディア州(Lombardy)の山地部を含む、3000〜3500m級の山地を「レポンティン・アルプス」(the Lepontine Alps)と呼び、その辺りが地質学では「レポンティン地域」と呼ばれているようです。
地質学的には、「ヨーロッパアルプス」のうちでも隆起量が非常に大きく、地下深部の構造が表れている場所とされています。
また「地質グループ」でいうと「ペニン系」の地質体が主体を占めています。ただし「インスブルック断層」(Insbric Fault)より南側(主にイタリア側)は、「サウスアルパイン系」です。
注6) ”Ma” は、百万年前を意味する単位です
変成岩に関する教科書類(文献5)、(文献6)には、「アンキ型」というものは記載されておらず、はっきりとは分かりません。一方、地学事典(文献17)では、「アンキ変成帯」(anchi zone)、「アンキ変成作用」(anchimet morphism)という用語の説明があり、それらの項から考えると、「変成相」でいうと「沸石相」(zeolite facies)、「ぶどう石・パンペリー石相」(prehnite-pumpellyite facies)など、低変成度(かなり低温、低圧条件下)の変成岩に相当するようです。(「イライト」という変成鉱物の結晶化度によって決める変成岩の分類方法であり、「変成相」や「変成分帯」で分類する一般的な方法とは異なる)。
注2) 「ペニン海」(the Penninic Ocean)について
中生代の「ジュラ紀」、「白亜紀」にかけて、「ヨーロッパ大陸ブロック」と「アドリア大陸ブロック」との間に、大西洋側からリフトゾーンを伴った細長い海域が形成されました(この連載の、第2―4章、第2−5章もご参照ください)。
この海域は、「ピエモンテ・リグーニア海」(Piemont-Liguria Ocean)や、「アルパイン・テティス海」(Alpine Tethys)など、文献によって様々に呼ばれ、一定していませんが、この連載では、「ペニン海」という名称で統一しています。
「ペニン海」はさらに、南側から順に、比較的幅の広い海洋である「ピエモンテ海」(the Piemont Ocean)、細長い半島状のゾーンである「ブリアンソン・ライズ」(Briançon rise)、幅の狭いリフトゾーンである「ヴァリストラフ」(Valais trough)、の3つの亜区に分けられます。この連載の第2部(古生代〜中生代のアルプス地域の地史)にも説明していますので、そちらもご参照ください。
注3) 「沈み込み帯」における「静的な圧力」と「動的な圧力」について
この件は「補足説明3」に、解る範囲でまとめてみました。
注4) 「コーサイト」について
「コーサイト」(coesite)という鉱物は、日本語では「コース石」とも呼びますが、化学組成は「SiO2」であり、石英(quartz)の高圧相にあたる鉱物です。両者には、結晶構造の違いがあるだけで、化学組成は同じです。
(文献9)によると、約2〜3GPa以上の圧力下では「石英」相より「コーサイト」相が安定となります(正確には温度(T)にも依存するので、その境界線(相転移ライン)は「P-T」図上で示され、低温側では約2GPa、高温側では、約3Ga)。
圧力(P)=2.5GPaとして深さを見積もると、静水圧条件(lithostatic)で、かつ地殻、上部マントルの密度を、約3g/cm^3と仮定すると、約75kmの深さに相当します。
注5) 「レポンティン地域」について
(文献1)では、「レポンティン地域」(the Lepontine area)や「レポンティン・ドーム」(Lepontine Dome)という言葉がしばしば出てきますが、(文献1)の地質図には場所が明記されていません。
(文献15)(ウイキペディア英語版の、レポンティン・アルプス)の項によると、「中部アルプス」のうち、スイス南部の、ティチーノ州(Ticino)を中心とし、その東側にあたるグラウビュンデン州(Graubünden)の西部や、その西側にあたるヴァリス州(Valais)の東部にかけて、及び国境を越えたイタリア北部のロンバルディア州(Lombardy)の山地部を含む、3000〜3500m級の山地を「レポンティン・アルプス」(the Lepontine Alps)と呼び、その辺りが地質学では「レポンティン地域」と呼ばれているようです。
地質学的には、「ヨーロッパアルプス」のうちでも隆起量が非常に大きく、地下深部の構造が表れている場所とされています。
また「地質グループ」でいうと「ペニン系」の地質体が主体を占めています。ただし「インスブルック断層」(Insbric Fault)より南側(主にイタリア側)は、「サウスアルパイン系」です。
注6) ”Ma” は、百万年前を意味する単位です
【補足説明1】; 「P-T図」、「P−T―t図」、「変成相」(metamorphic faceis)について
「変成作用」は一般に、地下深くの高圧、高温条件化で生じます。地下での圧力(P)は、大まかには深さ(D)に対応します。地下での温度(T)は、基本的には深いほど高温ですが、テクトニクス的な意味での場所によって温度は異なります。
そこで、変成岩の研究においては、まず圧力(P)と温度(T)をそれぞれ縦軸、横軸に採った図を作ります。そこに、「変成相」(metamorphic facies)、あるいは「変成相ゾーン」(metamorphic facies zone)と呼ばれる、いくつかのゾーンを設定します。このような図は、(文献5)では「温度―圧力図」と呼んでいますが、ここでは「変成相図」と呼ぶことにします。
「変成相図」はいくつか提案されており、文献によって「変成相」(ゾーン)の名称、種類、その範囲に違いがあります。図3に一例を挙げます。これは(文献5)の図10-1を引用したもので、元はLieu らの論文(1998)によるものです。
これらの「変成相」の名称は、原岩が玄武岩質(mafic)の岩石の場合における、典型的な変成岩の名称、あるいは典型的な変成鉱物の名称を使っているものであり、原岩の種類によって、各「変成相」における実際の変成岩の種類は異なることに注意が必要です
(例;「緑色片岩相」の条件で変成作用を受けたものでも、原岩が玄武岩質(mafic)な岩石だと、普通、「緑色片岩」となりますが、原岩が泥質岩(pelitic)だと「泥質片岩」になる、原岩が砂岩だと「砂質片岩」になる、など)。
この章に出てくる「変成相」としては、「エクロジャイト相」(eclogite facies)、「青色片岩相」(blue-schist facies)、「角閃岩相」(amphibolite facies)、「緑色片岩相」(green-schist facies)などがあります。この図にはありませんが、(文献1)で使われている「アンキ型変成(作用)」(anchi metamorphism)は、「沸石相」(zeolite facies)、「ぶどう石・パンペリー石相」(prehnite-pumpellyite facies)あたりに相当すると思われます。
「エクロジャイト相」は、「P-T」図上では上部(Pが大きい)の広い範囲を占めており、圧力(P)はだいたい、1.5GPa以上の範囲で、「高圧型」(あるいは「超高圧型」とも)の変成相とみなされるものです。(文献1−1)では、「青色片岩相」も「高圧型」の変成相としており、「角閃岩相」は「高温型」の変成相としていますが、解釈は文献によって様々です。
「P−T」図上に、実際のある地質体(岩体、鉱物でも)の受けた、圧力(P)、温度(T)の時間的履歴(t)を、一本の曲線で描いたものが、変成岩の研究では良く使われ、(文献1−1)にもいくつか載せられています。そういう図をこの章では、「P−T−t」図と呼ぶこととします。(文献1−1)では、その図上の曲線を「P−T−t path」と呼んでいます。
そこで、変成岩の研究においては、まず圧力(P)と温度(T)をそれぞれ縦軸、横軸に採った図を作ります。そこに、「変成相」(metamorphic facies)、あるいは「変成相ゾーン」(metamorphic facies zone)と呼ばれる、いくつかのゾーンを設定します。このような図は、(文献5)では「温度―圧力図」と呼んでいますが、ここでは「変成相図」と呼ぶことにします。
「変成相図」はいくつか提案されており、文献によって「変成相」(ゾーン)の名称、種類、その範囲に違いがあります。図3に一例を挙げます。これは(文献5)の図10-1を引用したもので、元はLieu らの論文(1998)によるものです。
これらの「変成相」の名称は、原岩が玄武岩質(mafic)の岩石の場合における、典型的な変成岩の名称、あるいは典型的な変成鉱物の名称を使っているものであり、原岩の種類によって、各「変成相」における実際の変成岩の種類は異なることに注意が必要です
(例;「緑色片岩相」の条件で変成作用を受けたものでも、原岩が玄武岩質(mafic)な岩石だと、普通、「緑色片岩」となりますが、原岩が泥質岩(pelitic)だと「泥質片岩」になる、原岩が砂岩だと「砂質片岩」になる、など)。
この章に出てくる「変成相」としては、「エクロジャイト相」(eclogite facies)、「青色片岩相」(blue-schist facies)、「角閃岩相」(amphibolite facies)、「緑色片岩相」(green-schist facies)などがあります。この図にはありませんが、(文献1)で使われている「アンキ型変成(作用)」(anchi metamorphism)は、「沸石相」(zeolite facies)、「ぶどう石・パンペリー石相」(prehnite-pumpellyite facies)あたりに相当すると思われます。
「エクロジャイト相」は、「P-T」図上では上部(Pが大きい)の広い範囲を占めており、圧力(P)はだいたい、1.5GPa以上の範囲で、「高圧型」(あるいは「超高圧型」とも)の変成相とみなされるものです。(文献1−1)では、「青色片岩相」も「高圧型」の変成相としており、「角閃岩相」は「高温型」の変成相としていますが、解釈は文献によって様々です。
「P−T」図上に、実際のある地質体(岩体、鉱物でも)の受けた、圧力(P)、温度(T)の時間的履歴(t)を、一本の曲線で描いたものが、変成岩の研究では良く使われ、(文献1−1)にもいくつか載せられています。そういう図をこの章では、「P−T−t」図と呼ぶこととします。(文献1−1)では、その図上の曲線を「P−T−t path」と呼んでいます。
【補足説明2】;「変成相系列」について
「変成相図」を元に、原点(温度T=0℃、圧力P=0Pa)から斜めに、傾きの異なる直線的な線(系列線)を引いたものを、「変成相系列」(metamorphic facies series)と呼びます(文献5)。
一般的には、傾きの異なる、3本の系列線が用いられます。
温度(T)を横軸、圧力(P)を縦軸に採った「変成相図」では、傾きが大きいライン(系列)を、「高P/T型」、「フランシスカン型」(Franciscan-type)、「高圧型」(high-pressure type)、「低温高圧型」などと呼びます。
傾きが小さいライン(系列)を、「低P/T型」、「ブカン型」(Buchan-type)、「アブクマ型」(Abukuma-type)、「高温型」(high-temperature type)、「高温低圧型」などと呼びます。
傾きが中間程度のライン(系列)は、「中P/T型」、「バロビアン型」(Barrovian-type)、「中圧型」(intermediate pressure type) などと呼びます。
(文献によって呼び方がマチマチで、(文献1)でも、「バロビアン型」、「高圧型」/「高温型」など入り混じって使われています。産総研「シームレス地質図」では、「高P/T型」などが使われています)。
これらの「変成相系列」は、それに対応する変成岩が形成されたテクトニクス的な地下の環境を反映していると考えられるので、変成作用が生じた時代の、テクトニクス的な解釈に利用されています。
添付の図6もご参照ください。これは、(文献5)の図10-12を引用したものです。
一般的には、傾きの異なる、3本の系列線が用いられます。
温度(T)を横軸、圧力(P)を縦軸に採った「変成相図」では、傾きが大きいライン(系列)を、「高P/T型」、「フランシスカン型」(Franciscan-type)、「高圧型」(high-pressure type)、「低温高圧型」などと呼びます。
傾きが小さいライン(系列)を、「低P/T型」、「ブカン型」(Buchan-type)、「アブクマ型」(Abukuma-type)、「高温型」(high-temperature type)、「高温低圧型」などと呼びます。
傾きが中間程度のライン(系列)は、「中P/T型」、「バロビアン型」(Barrovian-type)、「中圧型」(intermediate pressure type) などと呼びます。
(文献によって呼び方がマチマチで、(文献1)でも、「バロビアン型」、「高圧型」/「高温型」など入り混じって使われています。産総研「シームレス地質図」では、「高P/T型」などが使われています)。
これらの「変成相系列」は、それに対応する変成岩が形成されたテクトニクス的な地下の環境を反映していると考えられるので、変成作用が生じた時代の、テクトニクス的な解釈に利用されています。
添付の図6もご参照ください。これは、(文献5)の図10-12を引用したものです。
【補足説明3】;沈み込み帯における「静的な圧力」と「動的な圧力」について
(注3)で説明するつもりでしたが、結構ややこしい内容なので、この補足説明の項で、解る範囲で解説します。筆者自身が解ってなかったので、色々調べた内容をまとめたものです。
変成作用の教科書的(文献5)、(文献6)には、岩石、鉱物に加わった圧力は、対象となる岩石、鉱物に対し、深さに応じた「静的な圧力」(lithostatic pressure)(P0)が加わっている、と仮定して、そこから、「変成相図」なども利用して、変成作用が起きた深さ(D0)を推定します。
しかし最近では、プレート沈み込み帯においては、「動的な圧力」(dynamic pressure(P1))が加わっているのではないか、との意見がでて、活発に議論、検討されているようです。
この「動的な圧力」は過剰な圧力という意味で、地球物理学では、(tectonic over pressure)と呼ばれています(適切な日本語の訳語はないので、以下「動的な圧力」と記載)。
「静的な圧力」を(P0)、「動的な圧力」を(P1)と書くと、
合計の圧力 (P‘)=(P0)+(P1) となります(文献によっては、別の定義もある)。
その為、「動的な圧力」(P1)の影響を加えた圧力(P‘)から補正深さ(D‘)を求めると、補正前の深さ(D)よりも(D’)のほうが浅いことになります((P1)>0 として)。
ただし、沈み込み帯における「動的な圧力」(P1)を見積もるのは困難なので、補正深さ
(D‘)を定量的に求めることは困難です。
(文献1−1)では、「動的な圧力」(P1)は、「静的な圧力」(P0)と同程度、という仮定を入れ、補正深さ(D‘)は、補正前深さ(D0)の半分程度ではないか、という仮説にも触れられていますが、この仮説が正しいかどうか、私も良く解りません。
この連載、この章では、「動的な圧力」(P1)は考慮せず、「静的な圧力」(P0)のみの条件を仮定して、変成作用の起きた(推定の)最大深度(D0)を記載しています。
なお、(tectonic over pressure)に関しては、地球物理学ではホットなテーマらしく、検索すると多数の論文がヒットします。沈み込み帯における研究例として(文献12)、(文献13)を挙げておきます。
変成作用の教科書的(文献5)、(文献6)には、岩石、鉱物に加わった圧力は、対象となる岩石、鉱物に対し、深さに応じた「静的な圧力」(lithostatic pressure)(P0)が加わっている、と仮定して、そこから、「変成相図」なども利用して、変成作用が起きた深さ(D0)を推定します。
しかし最近では、プレート沈み込み帯においては、「動的な圧力」(dynamic pressure(P1))が加わっているのではないか、との意見がでて、活発に議論、検討されているようです。
この「動的な圧力」は過剰な圧力という意味で、地球物理学では、(tectonic over pressure)と呼ばれています(適切な日本語の訳語はないので、以下「動的な圧力」と記載)。
「静的な圧力」を(P0)、「動的な圧力」を(P1)と書くと、
合計の圧力 (P‘)=(P0)+(P1) となります(文献によっては、別の定義もある)。
その為、「動的な圧力」(P1)の影響を加えた圧力(P‘)から補正深さ(D‘)を求めると、補正前の深さ(D)よりも(D’)のほうが浅いことになります((P1)>0 として)。
ただし、沈み込み帯における「動的な圧力」(P1)を見積もるのは困難なので、補正深さ
(D‘)を定量的に求めることは困難です。
(文献1−1)では、「動的な圧力」(P1)は、「静的な圧力」(P0)と同程度、という仮定を入れ、補正深さ(D‘)は、補正前深さ(D0)の半分程度ではないか、という仮説にも触れられていますが、この仮説が正しいかどうか、私も良く解りません。
この連載、この章では、「動的な圧力」(P1)は考慮せず、「静的な圧力」(P0)のみの条件を仮定して、変成作用の起きた(推定の)最大深度(D0)を記載しています。
なお、(tectonic over pressure)に関しては、地球物理学ではホットなテーマらしく、検索すると多数の論文がヒットします。沈み込み帯における研究例として(文献12)、(文献13)を挙げておきます。
【参考文献】
(文献1) O. A. Pfiffner 著 “Geology of the Alps”, 2nd edition ,Wiley Blackball社刊,
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1); (文献1)のうち、6−1章(alpine metamorphism)の項
(文献1−2); (文献1)のうち、6−2章(the Cretaceous orogeny)の項
(文献1−3); (文献1)のうち、6−3章(the Cenozoic orogeny)の項
(文献1−4); (文献1)のうち、3−2章(Plate tectonics evolution
/Mesozoic)の項
(文献2) スイスのオンライン地質図
https://map.geo.admin.ch/#/map
(文献3) オーストリアのオンライン地質図
https://maps.geosphere.at/en
(文献4) 「ヨーロッパアルプス」の変成構造図(metamorphic structure of the Alps)
Oberhansli et al., 作成 (2004)
https://www.researchgate.net/publication/236671506_Metamorphic_structure_of_the_Alps_scale_11000000
※ このサイトは、”Reserchgate” という、論文等を集めたサイトで、その中に、
ヨーロッパアルプスの変成構造図がある。PDF版の地図を無料でダウンロードできる。
(文献5) 榎並 著 「現代地球科学入門シリーズ」 第16巻「岩石学」
共立出版 刊 (2013) (ISBN 978-4-320-04724-2)
のうち、変成作用に関する、第8章〜第13章
(文献6) 都城、久城 共著 「岩石学 2;岩石の性質と種類」
共立出版 刊 (1975)
のうち、変成作用に関する、第20〜21章
(文献7) ウイキペディア・ドイツ語版の、(Altkristalln)の項
https://de.wikipedia.org/wiki/Altkristallin
(2025年9月 閲覧)
(文献8) ウイキペディア英語版の、(Variscan orogeny)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Variscan_orogeny
(2025年9月 閲覧)
(文献9) ウイキペディア英語版の、(Coesite)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Coesite
(2025年9月 閲覧)
(文献10)
C. Chopin,
“Coesite and pure pyrope in high-grade blueschists of the Western Alps:
a first record and some consequences"
Contributions to Mineralogy and Petrology誌、vol.86,p 107?118,(1984)
(https: //doi.org/10.1007/BF00381838)
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00381838
※ 「西部アルプス」、「ドーラ・マイーラ」地塊での「コ―サイト」の発見の論文、
アブストラクトのみ無料で読める。
(文献11)
“IUGS” のサイトのうち、「ドーラ・マイーラ」地塊に関する解説
“The ultrahigh-pressure unit of the Dora-Maira Massif”
https://iugs-geoheritage.org/geoheritage_sites/the-ultrahigh-pressure-unit-of-the-dora-maira-massif/
※「ドーラ・マイーラ」地塊での「コーサイト」の写真などがあり、解説も解りやすい。
なお “IUGS” とは、(the International Union of Geological Sciences)
「国際地質科 学連合」という、地球科学に関する国際機関
(文献12)
F.O. Marques et al.,
“Tectonic overpressure at shallow depth in the lithosphere:
The effects of boundary conditions”
Tectonophysics誌、vol. 746, P 702-715, (2018)
(https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.03.022)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195118301276#:~:text=rights%20and%20content-,Abstract,pressure%20condition%20at%20the%20bottom.
※ (tectonic over-pressure)についてのシミュレーション研究
有料のサイトにつき、無料ではアブストラクトしか読めず、ちょっと解りにくい。
(文献13)
F. O. Marques et al.,
“Channel flow, tectonic overpressure, and exhumation of
high-pressure rocks in the Greater Himalayas”
Solid earth誌、vol.9,p1061?1078, (2018)
(https://doi.org/10.5194/se-9-1061-2018)
https://se.copernicus.org/articles/9/1061/2018/
※ 「ヒマラヤ山脈」における、(tectonic over-pressure)、
超高圧変成岩などについての論文
無料でPDF版をダウンロードできる。図が多いので多少はイメージがつかめる。
(文献14)
Frey M., F.Mahlmann R.,
“Alpine metamorphism of the Central Alps“
Swiss Journal of Geosciences Supplement 誌、vol.79. p135-154,(1999)
https://www.researchgate.net/publication/279612568_Alpine_metamorphism_of_the_Central_Alps
※ 「中部アルプス」、「レポンティン地域」における高温型変成作用に関する論文。
このサイトより、本論文のPDF版が無料で読め、ダウンロードもできる。
(文献15) ウイキペディア英語版の、(Lepontine Alps)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Lepontine_Alps
(2025年9月 閲覧)
(文献16) オックスフォード大学(英)の、地質学教育用資料のサイトのうち、
「変成岩」(Metamorphic Geology)のサイト(写真多し)
https://users.earth.ox.ac.uk/~oesis/teaching/metageol/
(文献17) 地学団体研究会 編 「新版・地学事典」 平凡社 刊(1996)
のうち、「アンキ変成帯」、「アンキ変成作用」、「後退変成作用」、
「コーサイト」、「沸石相」、「ぶどう石 パンペリー石相」、
「緑色片岩相」、「藍閃石片岩相」、「エクロジャイト相」、
「千枚岩」、などの項目
(2014); (原著はドイツ語版で、2014年にドイツの出版社刊)
(文献1−1); (文献1)のうち、6−1章(alpine metamorphism)の項
(文献1−2); (文献1)のうち、6−2章(the Cretaceous orogeny)の項
(文献1−3); (文献1)のうち、6−3章(the Cenozoic orogeny)の項
(文献1−4); (文献1)のうち、3−2章(Plate tectonics evolution
/Mesozoic)の項
(文献2) スイスのオンライン地質図
https://map.geo.admin.ch/#/map
(文献3) オーストリアのオンライン地質図
https://maps.geosphere.at/en
(文献4) 「ヨーロッパアルプス」の変成構造図(metamorphic structure of the Alps)
Oberhansli et al., 作成 (2004)
https://www.researchgate.net/publication/236671506_Metamorphic_structure_of_the_Alps_scale_11000000
※ このサイトは、”Reserchgate” という、論文等を集めたサイトで、その中に、
ヨーロッパアルプスの変成構造図がある。PDF版の地図を無料でダウンロードできる。
(文献5) 榎並 著 「現代地球科学入門シリーズ」 第16巻「岩石学」
共立出版 刊 (2013) (ISBN 978-4-320-04724-2)
のうち、変成作用に関する、第8章〜第13章
(文献6) 都城、久城 共著 「岩石学 2;岩石の性質と種類」
共立出版 刊 (1975)
のうち、変成作用に関する、第20〜21章
(文献7) ウイキペディア・ドイツ語版の、(Altkristalln)の項
https://de.wikipedia.org/wiki/Altkristallin
(2025年9月 閲覧)
(文献8) ウイキペディア英語版の、(Variscan orogeny)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Variscan_orogeny
(2025年9月 閲覧)
(文献9) ウイキペディア英語版の、(Coesite)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Coesite
(2025年9月 閲覧)
(文献10)
C. Chopin,
“Coesite and pure pyrope in high-grade blueschists of the Western Alps:
a first record and some consequences"
Contributions to Mineralogy and Petrology誌、vol.86,p 107?118,(1984)
(https: //doi.org/10.1007/BF00381838)
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00381838
※ 「西部アルプス」、「ドーラ・マイーラ」地塊での「コ―サイト」の発見の論文、
アブストラクトのみ無料で読める。
(文献11)
“IUGS” のサイトのうち、「ドーラ・マイーラ」地塊に関する解説
“The ultrahigh-pressure unit of the Dora-Maira Massif”
https://iugs-geoheritage.org/geoheritage_sites/the-ultrahigh-pressure-unit-of-the-dora-maira-massif/
※「ドーラ・マイーラ」地塊での「コーサイト」の写真などがあり、解説も解りやすい。
なお “IUGS” とは、(the International Union of Geological Sciences)
「国際地質科 学連合」という、地球科学に関する国際機関
(文献12)
F.O. Marques et al.,
“Tectonic overpressure at shallow depth in the lithosphere:
The effects of boundary conditions”
Tectonophysics誌、vol. 746, P 702-715, (2018)
(https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.03.022)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195118301276#:~:text=rights%20and%20content-,Abstract,pressure%20condition%20at%20the%20bottom.
※ (tectonic over-pressure)についてのシミュレーション研究
有料のサイトにつき、無料ではアブストラクトしか読めず、ちょっと解りにくい。
(文献13)
F. O. Marques et al.,
“Channel flow, tectonic overpressure, and exhumation of
high-pressure rocks in the Greater Himalayas”
Solid earth誌、vol.9,p1061?1078, (2018)
(https://doi.org/10.5194/se-9-1061-2018)
https://se.copernicus.org/articles/9/1061/2018/
※ 「ヒマラヤ山脈」における、(tectonic over-pressure)、
超高圧変成岩などについての論文
無料でPDF版をダウンロードできる。図が多いので多少はイメージがつかめる。
(文献14)
Frey M., F.Mahlmann R.,
“Alpine metamorphism of the Central Alps“
Swiss Journal of Geosciences Supplement 誌、vol.79. p135-154,(1999)
https://www.researchgate.net/publication/279612568_Alpine_metamorphism_of_the_Central_Alps
※ 「中部アルプス」、「レポンティン地域」における高温型変成作用に関する論文。
このサイトより、本論文のPDF版が無料で読め、ダウンロードもできる。
(文献15) ウイキペディア英語版の、(Lepontine Alps)の項
https://en.wikipedia.org/wiki/Lepontine_Alps
(2025年9月 閲覧)
(文献16) オックスフォード大学(英)の、地質学教育用資料のサイトのうち、
「変成岩」(Metamorphic Geology)のサイト(写真多し)
https://users.earth.ox.ac.uk/~oesis/teaching/metageol/
(文献17) 地学団体研究会 編 「新版・地学事典」 平凡社 刊(1996)
のうち、「アンキ変成帯」、「アンキ変成作用」、「後退変成作用」、
「コーサイト」、「沸石相」、「ぶどう石 パンペリー石相」、
「緑色片岩相」、「藍閃石片岩相」、「エクロジャイト相」、
「千枚岩」、などの項目
【書記事項】
初版リリース;2025年9月9日
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
ベルクハイルさんの記事一覧
※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
どなたでも、山に関する知識や技術などのノウハウを簡単に残して共有できます。
ぜひご協力ください!

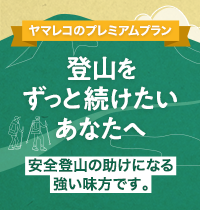








コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する